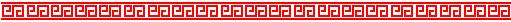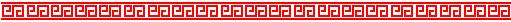第二回 妍娘々羞しめて襲衣の篇を謎す 鹽廷尉誤りて白虎廳に入る(その壱)
さてさて、師直の人となりは、悪賢くて欲深く、思うままに執事の権力を振るい、自分より優れた者を妬んで自分より劣った者を傷つけ、淫乱で、賄賂を貪り贅沢三昧、何をするにも不義不仁の振る舞いが多く、あの宋朝の太尉高きゅう※注1の性格そのままでございました。あちらは”高太尉”、こちらは”高執事”、姓もまた同じで、その毒悪を恐れぬ者とてありませんでした。
師直が淫乱から事件を引き起こし、遂に家を潰し身を損ない、永劫に人々の憎しみを受けているのをご覧じなされませ。誠に恐れ慎むべきは淫欲でございます。諺に「酒人を酔わしめず人自ら酔う、色人を迷わせず人自ら迷う」と申しますが、尤もなことでございますな。
ここに昔の方が色欲を戒める詩がありますが、このことを良く示しています。
花を貪りて費盡花を採るの心 身精神を損じ徳陰を損ず
汝に勧む花に遇ひてみだりに採ることを休めよ 仏門第一邪淫を戒む
さて、ここに卜部兼好※注2と言う一人の隠者がおりました。その頃は武蔵国久良岐郡六浦荘金沢※注3と言う所に住み、鎌倉から近かったので常々高階侯の館に赴いて、和歌を通じて交際しておりましたが、師直は貌好に贈る艶書をこの兼好に任せて書かせようと思い、ある日この人を招いて人気のないところに入り、艶書のことを頼むと、兼好は依頼を受けて暫く悩み、
「わしがこの艶書を書くのは姦通の取り持ちをするのと同じ事だ。わしは聖賢の書を読み、道を知り義を守る者だ。どうして不義の仲立ちなどして、徳を損なうことなどできようか。この人が風俗を乱し、人倫を失った輩だとは知らずに交際していたが、今後悔しても仕方があるまい。どうやってこの難題を逃れようか。」
と胸の内で戸惑いました。
師直はそれを見て、心急くままに、
「師兄、我が為に早く書いてくだされ。」
と責めました。
兼好が師直の様子を窺うに、深く恋に迷ったように見え、許してくれそうもなかったので、師直に背けば害を受けるだろうと恐れ、仕方なく承知して筆と紙を受け取り、そのまま一筆認めて師直に与えました。
師直はこれを見ると、世に抜きん出た文学の徒の手跡の上に文章が巧みで、風流な情が書き記されていたので、たとえ観音菩薩や西王母であろうとも、一度これを読めばたちまちぼーっとなって、色香に迷うだろうと思われました。
師直は大変喜び、兼好を重く賞して、急いでこれを金蒔絵の文箱に収め、封の上に『武蔵鐙』と言う三文字を書き付けました。これは自分が武蔵守なので、”かかる折りにや人は死ぬらん”※注4と言う歌詞の意をほのめかしたのでございましょう。
そして、気の利いた腹心の使いに申し含めて、貌好のもとに使わしました。
さて、その日の夕暮れ時、使いが戻ってきて、
「私めは急いで廷尉の館に行きまして、手蔓を求めて奥庭から入り、奥方の居間に近付いて様子を窺いますと、丁度奥方は浴室におりまして、湯浴みをされている御様子でしたので、上がるのを待って書簡を差し出しました。しかし、手に取って封じ紙をご覧になっただけでそのまま地上に投げ捨てられ、一言のお答えもなく奥の間に入られ、垂簾を下ろされましたので、どうしようもなく、人に怪しまれることを恐れて、書簡を拾い取って急ぎ帰って参りました。」
と言いました。
師直はこれを聞いて、心中鬱々として楽しまず、思いが募って、愚者のように酔ったように呆然たる有り様でした。
そして次の日、
「あの女が如何に厳しく貞操を守り、心が鉄石の如くであろうとも、元々女は水性のものじゃ。ひたすら我が心の誠を告げれば、よもや靡かぬことはあるまい。」
と考え、やがて一首の和歌を作って短冊に書き付け、再び使いを使わして、これを貌好に贈りました。その和歌はこのようなものでございました。
かへすだに てやふれけむと おもふにぞ わがふみながら うちもおかれず
貌好はこの和歌を見て別に言葉もなく、ただ”小夜衣”と答えたので、使いは帰ってそれを告げました。
師直はこれを聞いて、”小夜衣”の意とはなんであろうと考え、ようやくその謎を解き、
「そうじゃ、そうじゃ。新古今集釈教の部に、寂然法師※注5のこんな和歌があったな。
『さらぬだに おもきがうへの さよごろも わがつまならぬ つまなかさねそ』
これは仏門十戒のうちの不邪淫戒の意を詠んだ和歌じゃ。あの女がこの和歌の意で謎を掛けて辱めたと言うことは、事が成らなかったと言うことに違いあるまい。わしは今天下の執事として、天子大臣でさえ軽くは扱わず、将軍管領と雖も無闇に我が意を犯すことなく、天下に望んで得られない物とてないと言うのに、あの女がたとえ女御更衣だとしても、どうして再三わしに背いて我が心を苦しめ、その上辱めを与えて面目を失わせるのじゃ。きっと高貞にもこのことを語り、夫婦二人して笑っておるに違いない。どうしてこの恨みを忍べようぞ。よしよし、いずれ兵馬を集めて高貞の館を踏みにじり、女を奪ってこの鬱憤を晴らしてやろうぞ。なんと薄情な女じゃ。」
と怒り恨んでいる折りも折り、取次の者が山名次郎右衛門の訪問を告げました。
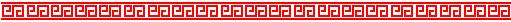
※注1:漢字は”にんべん”に”求”。お馴染みですね。
※注2:一般に吉田兼好の名で知られていますね。『徒然草』の著者です。
※注3:現在の神奈川県横浜市金沢区ですな。
※注4:作者不明、在原業平を主人公にしていると言われる『伊勢物語』の十三段が以下の通り。
昔、武蔵なるおとこ、京なる女のもとに、「聞ゆれば恥づかし、聞えねば苦し」と書
きて、上書に「武蔵鐙」と書きてをこせてのち、をともせずなりにければ、京より
女、
武蔵鐙さすがにかけて頼むには問はぬもつらし問ふもうるさし
とあるを見てなむ、堪へがたき心地しける。
問へばいふ問はねば恨む武蔵鐙かゝるおりにや人は死ぬらん
※注5:寂然法師は、『新古今集』撰者の寂蓮法師とは別の方です。”十戒歌”の一つとして出ています。