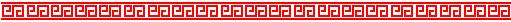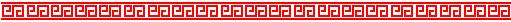第七回 密書を奪てイ票兒節に死す 釵兒を擲て大星號を示す(その壱)※注1
その時勘平は、去る年鎌倉に潜入して乞食に身をやつし、仇を討とうと密かに師直を狙ったことを始めとして、夜叉老婆が角兵衛が密通し、イ票兒を騙して遊郭に売り与一兵衛を毒殺した事、そして夜叉老婆と角兵衛を殺して舅の仇を報いた事などを最初から最後まで詳しく話したので、弥五郎も裏山で猪を打ち殺したことを話して、互いの身の無事を喜びました。
さて、弥五郎が更に言うには、
「夜叉老婆たち二人の言動を聞けば、将に大罪に値するものじゃ。しかし、賢弟はこれをお上に訴えず、私怨を晴らしたからには、法を犯したことになる。早くこの地を逃れ去らねば、密計がつまずかないとも限らない。わしは賢弟を連れて郷右衛門殿の隠れ家に行き、大星殿に願って賢弟の望みを遂げさせようと思うがどうじゃ。」
勘平は、
「もしそうなれば、我が身のためには無上の喜びです。全て貴兄にお頼みいたします。」
と言って大いに喜び、遂に二人は急いで麓に下りました。
それはさておき...
[金夫]※注2九太夫は、前の年郷右衛門のために蓄えた財産を失ってから、生活する手段もなくどうしようもないまま、一つの手蔓を求めて師直に内通し、間者となって京都にいて大星の腹の内を探り、日々鎌倉に飛脚を走らせて密かにその様子を告げ知らせておりましたが、師直は大星が遊び狂っているのを聞いて半ば信じ半ば疑い、あれこれ心休まることもありませんでした。
しかしこの頃、京童の戯れ歌にこんなものがありました。
一人貫きて事を作し 日生連なりて功を立つ
刺蜂蛛網に死し 還りて時世隆ならしむ
「一人貫きて事をなす」と言うのは、一人を貫けば乃ち”大”の字で、「日生連なりて功を立つ」と言うのは、日生を連ねれば乃ち”星”の字となり、事を成し功を立てる人は大星の身に応じております。第三句の「刺蜂」と言うのは、師直の奸悪が毒蜂が人を損なうことに喩えており、「蛛網に死す」とは、大星らが天網地網を借りて遂には仇を報いる兆しで、最後の一句は奸臣が滅んで再び太平無事の日々が戻ると言う意味でございます。
この戯れ歌は全て師直の身に関わるとは言え、師直は益々権威を弄び、少しもその意を悟ることはありませんでした。
やがて時は過ぎ、この年は既に北朝の康永元年でございました。
しかし、師直は大星の品行を不安に思い、家臣の鷺坂伴内に命じて、尚も大星の心中を探らせました。
このため、伴内は急いで旅支度を整え、昼夜の別なく京都に上り、九太夫と心を合わせてあの手この手の計を用いました。
そしてある日、伴内は大星を試そうと九太夫に案内させ、当地の色街に行き、まずその様子を見ると、真に別世界のようで目も眩み心も油断するばかりでした。
伴内は欲界の仙都、昇平の楽国とは、この地のことに違いないとひたすら賞賛し、心中大いに興味をそそられ、九太夫と共にこの地で最も有名な遊郭である「一李逵家」※注3の門前にやってきて見ると、門に一片の額を掛け、「待来送帰」と四文字が彫られてありました。
建物の造りは見事で、庭の造作も落ち着いており、一間ごとにいくつもの銀の燭台を置いて、まるで真昼のような有様でございました。
二人が直ぐに門口に立つと、俄に笛太鼓三味線の音が響き渡り、こんな歌が聞こえました。
花発く祇園の裏 玉簪羅綺連なる
東西極楽国 赫奕人をして眩せしむ※注4
九太夫がまず先に進み、
「馴染み客が来たと言うのに、何故迎えに出ないのじゃ」
と大声で叫ぶと、紅前掛けの仲居が急ぎ出て来て、
「どなた様かと思えば九大官人※注5でございましたか。この頃はご光臨絶えて久しゅうございましたが、今日は如何なる風の吹き回しで、我が家へいらっしゃいましたやら。」
と満面の笑みで言いました。
九太夫は、
「今日は初めての客人を一人連れて参った。酒を呑もうと思ったが、見れば客が多い様子、小座敷でも良いので空き部屋はないか。」
と言うと、仲居が申しました。
「今晩は、あの由良大老官が多くの名妓を揚げて遊んでおられますので、客座敷は全てふさがっております。ただ、一間二階に空き部屋がございまして、狭いとお思いではございましょうが、一つ我慢してお遊びいただけませんか。」
九太夫、
「その空き二階はきっと蜘蛛の巣だらけであろう。」
仲居、
「お殿様もお口の悪い。」
九太夫、
「いい歳をして、女郎の蜘蛛の巣に捕らわれるのを怖れたまでじゃ。」
とふざけると、仲居はホホホと笑いながら、
「さぁさ、こちらへお上がりくださいまし。」
と言って、二人を案内して二階に上げました。
さて、大星はこの夜ここの奥座敷で酒宴を設け、名のある芸妓を集め、旨い酒善い肴を供えて大いに酒盛りをしておりましたが、悪酔いした勢いで芸妓たちに向かって、
「かつてわしが『致虚雑爼』と言う本を読んだ時、唐の玄宗皇帝が楊貴妃と共に明月の元で錦の布で目隠しし、狭いところで鬼ごっこをして遊んだが、これを『捉迷蔵』と名付けたとあった。今、この酒盛りも興が尽きようとしておるから、わしも玄宗にならってお前たちと鬼ごっこをして、捕らえた者には大杯の罰酒を呑ませて、また興を盛り上げようと思うが、お前たちはどうじゃな。」
と言うと、皆賛成して、
「それは面白い遊びでございますね。さぁ、早く始めましょう。」
と言って大騒ぎしたので、大星は手拭いで目隠しして、『捉迷蔵』を始めました。
歌い手や仲居も芸妓に混じって散らばり、手を打って走り楽しみました。大星はふらふらして両手を前に伸ばし、辺りを探ってこれを捉えようとしました。あたかも盲目の亀が水中を歩くようでもあり、伯牙※注6が琴を掻き鳴らすようでもありました。
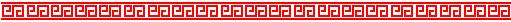
※注1:この回は『仮名手本忠臣蔵』で言うと第七段の一力茶屋の場面になりますな。
※注2:「金へんに夫」で”おの”と読みます。前出。
※注3:『仮名手本忠臣蔵』では一力茶屋ですが、そこはそれ、水滸の引っ掛けっすね(笑)
※注4:『仮名手本忠臣蔵』では、「花に遊ばば祇園あたりの色揃へ、東方南方北方西方、弥陀の浄土がぬりに塗立てぴつかりぴかぴか、光りかがやくはくや芸子にいかなすいめも、現ぬかして、ぐどんどろつくどろつくや」とありますな。
※注5:これも水滸風っすね(笑)この辺り、呼称は軒並み中国風になってます。
※注6:『列子』や『呂氏春秋』に登場する人で、琴の名手。友人鐘子期はその才能を賞賛したが、その鐘子期が死ぬと愛用の琴を壊し弦を切って、二度と琴を弾かなかったと言う。本当はもちっと色んなエピソードがありまっす。が、なんでここに登場するのか、さっぱり関連がないので京伝に聞いてみたい(笑)