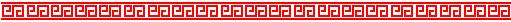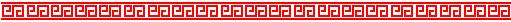
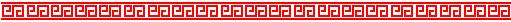
| 水滸伝 虚構の中の史実 中央公論社 |
| 宮崎市定氏著。氏は子供の頃から水滸伝が好きだったそうで、研究書なんだろうけど、すごくいい本です。東洋史学の人なので、時代背景等参考になります。私が持っているのは新書ですが、文庫もあります。 |
| 梁山泊 水滸伝・108人の豪傑たち 中央公論社 |
| 佐竹靖彦氏著。同じ研究書でも、こちらは文学として水滸伝を解説している部分が多くて、成立過程等が詳しい。公孫勝がいる理由を読んで、思わず唸ってしまった。 |
| 水滸伝の世界 大修館書店 |
| 高島俊男氏著。私が読んだ水滸伝研究書の中でも、一、二を争う出色の内容。読んでいて、文章が面白いです。文章がうまいんでしょうね。論文をここまで読ませる人も珍しい。 |
| 水滸伝と日本人 大修館書店 |
| 高島俊男氏著。前述の本を書いた時、書き過ぎて削ったものに書き足して出した本だそうですが、どうしてどうして...他の研究書とちょっと違った角度からの内容で、題名のように日本で過去に出版された水滸伝の訳本や水滸伝に関連する小説の解説です。それぞれの訳本から同じ部分を抜き出して比較したりしていて、非常に面白いです。 |
| 「水滸伝」を読む 梁山泊の好漢たち 講談社 |
| 伊原弘氏著。組織、都市、旅、金などの観点から水滸伝の歴史的背景を論述されてます。金に関する部分は面白いんですが、それ以外のところは”水滸伝”と言う目で見るとちょっと掘り下げ方が浅いような気がします... |
| 豪傑水滸伝 梁山泊一〇八星の世界 光栄 |
| 實吉達郎氏著。基本的に好漢の紹介が主なんですけど、引用している資料が凄まじい。よくもまぁこんなに水滸に関連する資料を集めたもんだと感心させられます。この方も水滸大好きのようで、面白いです。 |
| 水滸伝の謎 強盗がヒーローになるとき 光栄 |
| 岡崎由美氏監修。光栄にしては珍しい、論文中心の本です。でも、そんなに難しく書いてないので、論文を読み慣れていない人でも取っ付き易いかな。斬新な宋江論が光ります。構成的にも面白い章立てになっていて、水滸伝のバックグラウンドを知りたい人には良いでしょう。 |
| 90分でわかる 水滸伝の読み方 かんき出版 |
| 鶴島俊一郎氏監修。沿革とエピソードごとに2ページ程度にまとめたあらすじ、ちょっとしたコラムで構成されています。絵とか図表入りでの解説が付いているので、ちょっとかじってみたい人にはいいかも。でも、”90分でわかる”かどうかは保証出来ませんよ、私は... |
| 水滸伝 天導一〇八星好漢FILE 光栄 |
| シブサワ・コウ氏編。これはゲーム本っぽいけれど、さにあらず。登場人物全てにわたって解説がなされています。本編を読む時のガイドブックとして最適。 |
| 水滸伝 天命の誓いガイドブック 光栄 |
| シブサワ・コウ氏監修。おまけ。本箱整理してたら、出て来ました。10年位前のゲーム本。ファミコン版だけど、PS版も地形が同じなんだよね。 |
| 武器と防具 中国編 新紀元社 |
| 篠田耕一氏著。中国の武器について、イラストと文章で解説。これを見つけるまで呼延灼とかが使う鞭って、インディ・ジョーンズか女王様が使う鞭が金属でできてるんだと思ってました(^^; |
| 東京夢華録 平凡社 |
| 入矢義高、梅原郁氏訳。丁度水滸伝の時代の頃の孟元老と言う人が書いた東京開封府の地理誌と風土記。北宋が滅んだ後の南宋で往時を懐かしんで書かれてものらしい。この本の面白いところは、庶民生活の部分になるほど記述が活き活きしているとこですね。水滸伝の補助参考書には持ってこいです。 |
| 世界の歴史 宋と元 中央公論社 |
| 宮崎市定氏責任編集。「世界の歴史」の6巻目に当ります。サブタイトルが宋と元となっていますが、7割以上が宋について書かれています。ただ単に歴史上の出来事が政治、経済、軍事、文化と幅広く説明されていて、えらく参考になります。特に宮崎先生ですので、至る所に水滸伝を引用されていて私的にはすごく嬉しいかも。ちょっと立ち寄った古本屋で100円でGET。お薦めです。 |
| シルクロードをゆく 付・「水滸伝」の旅 東方書店 |
| 駒田信二氏著。あの駒田先生の紀行文です。シルクロードもいいんですけど、「水滸伝」の旅。文章は淡々としていて、どちらかと言うと飄逸な筆致で書かれているんですが、電車で読んでいて不覚にも涙が溢れてきました。駒田先生ならではの紀行文と言えます。 |
| 水滸詞典 漢語大詞典出版社 |
| 胡竹安氏編。水滸伝の中に出てくる古語専門の中国の辞典です。表紙の絵と題字は戴敦邦さんが書かれてます。はるか昔、大学の第二外語で習った中国語がこんなところで役に立とうとはお釈迦様でも気が付くめぇ(笑)が、もうちょっと真面目にやっとけば良かった...で、中身は簡体字で書かれてます。でも、中日辞典があれば恐くない!原文読むのに水滸詞典使って、水滸詞典読むのに中日辞典使うのかっ |
| 正岡子規集 改造社 |
| 正岡子規と言えば、知る人ぞ知る明治の偉大な俳人。今まで全然縁のない人だったけど、古本市で何気なく手に取って狂喜乱舞。評論「水滸伝と八犬伝」の全文が出てるぢゃありませんか。高島俊男さんの本で一部を読んだことはあったけど、忘れていたのでありました。「八犬伝」の評については「八犬伝」の原典を全部読んでないのでコメントできませんが、「水滸伝」についての評は名文です!流石は十七文字でイメージをビジュアル化する、言葉のマジシャンであると言へませう。十九頁ほどの短い文章ですが、こりゃあ面白い! |
| 水滸伝・任侠の夢 NHK出版 |
| 平岡正明氏著。NHKのBSで放映した「水滸伝・義侠の夢」の取材旅行の紀行文。文章そのものは結構いい加減なものなんだけど、真剣に読まなけりゃまぁ面白いのかな?主に山東が中心で、水滸にまつわる民間伝承とか好漢の子孫!とかも出てきます。私的には本文よりも最後に付いている、取材旅行に同行した中国の考古学者、黄波さんが書いた「水滸伝故里紀行」が断然面白い。採集した民間伝承、好漢の子孫達について、本文より突っ込んで書かれていて、『百聞は一見に如かず』とはこのことかと思わされます。俺も行きたい〜! |
| 少林拳と太極拳 中国武術 新人物往来社 |
| 松田隆智氏著。古本市で安かったので買ったんだけど、やっぱり出てます水滸伝。武松が水滸伝中で使う技が二郎門拳と言う流派にあるとか、魯智深の酔拳の話だとか(こっちの世界では酔拳は武松より魯智深みたい)、魯智深の瘋魔杖の話だとか(禅杖のことかな?)、他にもいっぱい出てきます。文学系の資料じゃないので、いつも見慣れてるような話以外が多くて面白いです。 |
| 水滸伝人物事典 講談社 |
| 高島俊男氏他著。我らの仲間、『水滸伝袋』の犬大将さんが出版まで8年間も携わったと言う曰く付きの事典です。駒田氏訳120回本から全ての登場人物を抜き出して、登場回数・解説・コメント等が付けてあります。付録として宋代の官制・武器・年表・地図等も付いていて、絵も犬大将さんが書かれています。うぅ、頭が下がる(涙) |
| 中国史稿地図集 下冊 中国地図出版社 |
| 中文書籍の歴史地図集。これは下巻で隋から清までの地図が載ってます。店によって、千円前後なんでお手軽です。本当はもっと詳しい地図も出てるんだけど、高くて買えません(汗)面白いのは、宋代に宋江起義と方臘起義として、それぞれ地図が出てること。方臘起義の方は官軍と農民軍?の進撃路とかが書かれていてなるほどなんだけど、宋江起義の方は...なんか意味あるのか、この地図(汗) |
| 中国歴史地図集 第六冊 宋・遼・金時期 地図出版社 |
| 中文書籍の歴史地図集。上の『中国史稿地図集』で言ってるもっと詳しい奴です。神保町で4,000円もしたのに、中華街で1,000円ちょいだったんで買っちゃいました(汗)まぁ、水滸伝の成立時期は元とか明とか言われてますし、元々水滸伝は小説ですから、宋代の歴史地図見たからって、どうなるもんでもないとは分かってるんですけども(笑) |
| 歴代官制・兵制・科挙制表釈 江蘇古籍出版社 |
| 中文書籍の資料なんですけど、こんなの欲しいなぁと思ってたんで、ビンゴです。史学なんて縁がなかった私としては、『宋史』とかだと流石にちょっと全部は見れないし...素人向けの参考書籍としては値段も安いし、有り難いです〜 |
| 水滸計謀鑑賞 山東人民出版社 |
| これ、序言によれば歴史学者で兵法、特に謀略を研究してる人と文学研究してる人の合作で、水滸伝を謀略学的角度(?)から解読した本なんだそうです。謀略学って学問があるとは知らなかったなぁ...でも、水滸伝って陳平みたいな戦略的謀略はないから、苦労したんだろうな(笑)内容的には100回本水滸伝中の謀略(って言うか策略程度だけど)をピックアップして、七書・二十四史・左伝その他を引用しつつ解説してます。水滸の登場人物を史料上から検討したりもしてます。ちょっと水滸研究の観点としては特異だし、兵法的解釈ってのが面白いです。学問として成り立つのかどうかは私には分からないですけども... |
| 怖くて読めない水滸伝 講談社 |
| 実吉達郎氏著。水滸伝から”残虐”と思われる部分をピックアップして、当時の中国の習俗とかから文化人類学的っつーか民俗学的っつーか解説をした本です。水滸伝自体を紹介する内容の本ではないです、念のため。所謂ここんとこ流行ってる”本当は怖い”系の本なんだけど、どーにかならんかこのタイトル(笑)グリムとかと違って水滸伝って童話じゃないし、言ってみれば犯罪者集団のお話だから怖くて当然じゃん。何を今更(爆)この手の本が流行るのも世紀末のせいなのかな?日本人から見て”残虐な習俗の小説”であることと、最近の”信じがたい犯罪心理の事件”、後者の方がよっぽど怖いと思うのは寨主だけ? |
| 中国小説史研究 -水滸伝を中心として- 汲古書院 |
| 中鉢雅量氏著。所謂学術論文集です。第一部が小説史の流れについて、第二部が水滸伝研究の論述になっています。第二部は水滸伝の成立史、成立の歴史的背景、金聖嘆の批評について、季節描写、水滸伝中の鬼神信仰などが主な内容です。いや〜、久しぶりに論文ってものを読みましたけど、結構面白いです。水滸伝が好きだからかも知れないけど(笑)高い本なので買うのはちょっとですけど、図書館なんかで見つけたら一見の価値ありです。著者の”水滸伝の作者は好漢達を哀惜してやまなかった”と言う所見、わしも大賛成! |
| 鴎外選集第十二巻 評論・随筆二 岩波書店 |
| ご存じ明治の文豪森鴎外の全集の中の一冊ですが、この中に『標新領異録(抄)-水滸伝』があります。明治期に相当の権威があった文学雑誌『めさまし草』に載った合評企画のうちで水滸伝を扱った回のものですけど、メンバーが凄い。鴎外の他に超有名なところでは、幸田露伴なんて人も入っていて、6人の合評になっています。所謂水滸伝の解説本にあるような項目は一通り述べられていて、特に凄いのは鴎外が「宋代の支那と今の支那とには同一顕象があって、それがこの書中に影を印して居て、随って水滸伝はどこまでも特殊なる支那産たることを失せぬと言ふのだ。」と言う論を受けて、森田思軒と言う人が評論している部分で、なぜ水滸伝に出てくるような事象が中国では起こるのかを理路整然と書いています。これははっきり言って凄いです!明治の人達は凄すぎる! |
| 水滸傳と支那民族 大東出版社 |
| 井坂錦江氏著。なんて言ったらいいんだろ?水滸伝から政治・思想・宗教・社会・習俗・政情・学芸・衣食住・経済・法律・武芸軍事・動植物と言ったジャンルで事例をピックアップして”中国を知ろう”と企画したような本とでも言いますか...発行された昭和17年と言う時代背景があるのかも知れませんな。前半の補完のため、後半に百二十回本の粗筋が付いています。で、メインの前半ですけど、ピックアップしたものについての考察が若干書かれています。ん〜、私が思うに、著者は水滸フリークではないな。山路愛山と言う人に『支那と支那人を知るには支那の小説を読むに限るよ。』と言われて、全くのお勉強で読んだんでしょうね。だから、参考にはなるけど、ちょっと物足りない。誤植も多いけど、誤植とも思えない間違いがやけに目に付いたってのも、そう思う一因なのかも... |
| 水滸伝与三十六計 解放軍文芸出版社 |
| 姚有志氏編著。これも中文書籍なんですが...水滸伝と三十六計なんて、私をターゲットに書いて頂いたような本です(喜)どっちかって言うとここに入れるよりも『兵家書房』に入れるべき内容なんだけど、うちは水滸メインだからこっち(笑)つまり、水滸伝の紹介でなくて、水滸伝上の逸話を使って『三十六計』を説明していると思ってください。なので、それぞれの計の文章は、その計略の概略・水滸伝上の該当部分の抄出・解説からなります。『中国劇画 孫子の兵法』の『三十六計』&『水滸伝』版と言えましょう。 |
| 東洋文化研究所紀要 第百二十二冊 東京大学東洋文化研究所 |
| この中に高島俊男先生の書かれた『宋江實録』と言う論文があって、高島先生の「史実の宋江論」が論述されています。この論議については、過去から日本でも中国でも多くの学者が論じていて諸説紛々、中でも比較的有名なのが、宮崎市定先生が『水滸伝 虚構の中の史実』でも述べられている「宋江二人説」です。が、高島先生のこの論文では、筆鋒鋭くその説を論破されています。高島先生の説の主旨は、「史実の宋江は張叔夜に招降された草賊宋江のみで、その宋江は方臘戦には参戦していない。その後に現れる宋江は、宋江の名を騙る別の草賊である。」と言うもので、宋江論の論拠となる史料の検証を軸に論を展開されています。私みたいな門外漢が言うと怒られるかも知れませんが、もの凄くドライブ感のある論文です。手に汗握ると言いますか...前から一度読みたいと思っていたんですが、本当に面白いです。よんたい賢弟、多謝! |
| 中国文明の歴史6 宋の新文化 中央公論社 |
| 佐伯富氏責任編集。中公文庫のシリーズものの中の一冊で、宋代中心の巻です。歴史上の事件だけでなくて、社会背景とか生活・文化とかも比較的詳しく書いてあって分かり易いです。あと、遼・金・西夏なんて言う、宋の周辺諸国の記述が懇切丁寧に書いてあって嬉しいかも。文化に関しては日本と宋の関連についても章立てされています。どっちかって言うと固目の本なのに、なんだかとっても面白い。お勧めですよ。 |
| 水滸語詞詞典 上海辞書出版社 |
| 李法白・劉鏡芙両氏編。『水滸詞典』同様、水滸伝の中に出てくる単語専門の中文辞書です。『水滸詞典』は『水滸全伝』を元にしていますが、こちらは百回本を元にしています。でも、先頭に数葉附いてる挿し絵は『水滸全伝』のもの(笑)語数で言うと『水滸詞典』の4,895項目に対して3,194項目です。とは言え、『水滸詞典』に無い語句が出ていたり、他書での用例も『水滸詞典』と良い勝負だったりします。附録として簡単な版本解説と好漢の綽名の解説があるんだけど、これが結構面白かったりします。って、ちゃんと読めてる分けじゃないけどね(笑) |
| 水滸興武打芸術 江蘇古籍出版社 |
| タイトルを読めば分かる通り、武術的な面から水滸伝の記述を検証しようと試みた本です。とは言え、一概にそればっかが書かれてるわけでもありません。こう言う切り口の本って、ありそうでなかったんでちょっと新鮮かも。表紙にいきなり『好漢歌』の歌詞がある辺り、中央電視台水滸のHITで連鎖出版された本なのかな? |
| 水滸伝 108星のプロフィール 新紀元社 |
| 遂に出た?新紀元社の水滸本です(笑)絵がなんつーか...まぁ、それはさておき、誤字も...それもさておいて、この本のポイントはなんと言っても年表です。年表たって、水滸伝の出来事年表じゃないよ。好漢一人一人の年表よ(驚)いや〜、これは本当に驚きました(汗)大したもんです。簡単に言っちゃうと、光栄の『水滸伝 天導一〇八星好漢FILE』の初心者向けって感じなんですけど、好漢一人ずつに関連する本編のエピソードが全部書かれてて、どこから読んでも断片的ではあるものの楽しめます。 |
| 癸辛雑識 中華書局 |
| 縦書き繁体字のエッセイ集みたいな本です。これを書いた人は宋末元初の周密って人なんですが、この本の中の一節にキョウ聖与(花項虎キョウオウのキョウです)さんの書いた『宋江三十六人賛』の賛の部分が全部載ってます。これ、一句四文字の四句で一人分の賛になってます。晁蓋が入ってたり、渾名が『水滸伝』と違っていたりして、興味深いもんがあります。参考までに「孫二娘之酒肆」に載せてみますので、見てみてね。でも、読めない所あるから訳は無しだよ〜ん(笑) |
| 人物 中国の歴史 中国のルネサンス 集英社 |
| 陳舜臣氏責任編集。これもシリーズものの中の一冊で、唐末〜元初の巻です。取り上げられているのは朱全忠・趙匡胤・王安石と司馬光・歐陽修と蘇軾・徽宗・岳飛と秦檜・朱子と陸象山・チンギスハンです。私的には王安石&司馬光が一番面白かったかなぁ。1ページだけですけど、徽宗の後に宋江のコラムがあります。ちょろっと宋江論が書かれてあって、宮崎市定先生の”宋江二人説”を採用してますな。 |
| 宋代官制辞典 中華書局 |
| 中文の宋代限定のB5版の官制辞典です。沿革・職掌・官品・編成・簡称別名等の項目で説明が付いてます。『水滸伝』に出てくる官名とかは、宋代・元代・明代が混じってるってのは良く聞く話なんで、これで何をどうしようってことではないんですけど、ちょっと何か調べたい時に手元に資料がないと気が済まない性分なんですわ(汗)まぁ、田舎なもんで近所にまともな図書館がないってのが原因ではあるんですけどね...でも、「ふーん、そうなんだ」的に面白くって、結構気に入ってます(笑)が、普通素人の一社会人が買うような本でないことも確かだ(汗) |
| 支那遊記 ほるぷ |
| 芥川龍之介著。本当は大正15年改造社出版の本ですけど、これは完全復刻した昭和52年の本です。タイトル通り、芥川龍之介の紀行文、と言うより随筆に近いです。なんか、中国に対する悪態と愚痴の連続のような気もするな(笑)上海・杭州あたり、この前の中国オフで行ったばかりで、数十年の時を経ても共感できる部分もあったりして。んで、なんでこの本が水滸関連かって言うと、あっちこっちに水滸が顔を出してるんです。大体の所は高島先生の『水滸伝と日本人』に引用されてますけど、芥川良く『水滸伝』知ってますな(喜)ちょろっと水滸が引用されてたりすると、つい嬉しくなっちゃう(爆)この中で短いですけど、芥川の水滸感が語られてて、これまた共感しちゃうんだなぁ... |
| 中国古典紀行4 水滸伝の旅 講談社 |
| 陳舜臣氏監修。1981年刊の写真主体の紀行本。文章を書いてる人達は豪華で、陳舜臣さんは当然のこと、駒田先生、横山光輝氏、伴野朗氏、草森紳一氏なんて人たちも書いてます。駒田先生が書いてるところは「八犬伝と水滸伝」、高島先生の『水滸伝と日本人』を彷彿とさせます。また、横山氏の文章によれば、出版社から「『水滸伝』描いてくれ」と言われて初めて読んだんだって(汗)草森氏の宋江論も面白いなぁ。もう20年も前の本だから、今はこれで見る風景とはまた違ってるんだろうけど、この目で見たい!梁山泊!!あー、もう、行きたい行きたい行きたい!!! |
| 唐話辞書類集 第二十集 汲古書院 |
| これはタイトルから判るかな?江戸時代の”中国語会話辞書”のシリーズなんですけど、この巻には『聖嘆外書水滸傳記聞』と『水滸傳抄解』の影印が載っています。『聖嘆外書水滸傳記聞』は第二十六回から第七十回までの本文と金聖嘆評中の語句解説で附録で百二十回本の語句解説も付いてます。『水滸傳抄解』は楔子から第十一回までの語句解説で、日本語版の『水滸詞典』みたいなものです。いずれも刊本(印刷出版された本)じゃなくて、写本(手書きの本)です。『水滸傳抄解』の方が見やすいかな?このシリーズは、他にも第三集と第十三集も水滸の辞書集になっています。 |
| 水滸伝 梁山泊の英雄たち 新人物往来社 |
| 『別冊歴史読本第二十一巻十一号』です。十数名の好漢のエピソード紹介、と言うか短編小説に近いものがメインですが、歴史的背景、成立の概要、日本の翻案小説紹介、武芸十八般、書籍&グッズ紹介、水滸後伝あらすじ、登場人物紹介、地図など幅広く紹介されていて、割と良くできている本だと思います。筆を取っておられる方々もしばしばお見かけする方が多いです。これと言って目新しいと言うわけではありませんが、それ故に王道を行く本だと言えましょう。ただ、’96年発行なんでもうバックナンバーの在庫ないだろうなぁ...わたしもこれ買いそびれて、手に入れるのに5年掛かったんだから... |
| 週間朝日百科 世界の文学 107 朝日新聞社 |
| 三国志演義、水滸伝の特集号です。と言っても、全部合わせても30ページちょいの雑誌だけど(笑)水滸はそのうち8ページ分。内容は、版本の簡単な説明、好漢数人の概要、成立過程の概説、幸田露伴と『水滸伝』などなど。ALLカラーの雑誌なので、写真その他が綺麗ですな。水滸の年画とかも良いっす。つーか欲しい(笑)それ以外にも、『隋唐演義』『楊家将演義』(?)『説岳全伝』とかもちらっと出てます。 |
| 露伴全集 第十八巻 研究 岩波書店 |
| 昭和二十四年発行の本で、大正から昭和初期にかけて幸田露伴が各誌に掲載した文学・道教など全て中国関係の研究論文集です。この中で『水滸傳の批評家』『水滸傳各本』『支那文學と日本文學との交渉』などが『水滸伝』について言及されたものです。現在の研究レベルから言えば間違っている部分もありますが、それでも鋭い指摘は多いかも。最初の論文では、金聖嘆について「李卓吾の真似じゃん!」とこてんぱんにした後、李卓吾の紹介が結構詳しく書かれています。二つ目は版本解説で、百二十回本を百回本より旧本だとしているけど、どうも百回本については過去にちらっと見掛けたくらいで、内容を精査できなかったみたいです。三つ目は建部綾足や馬琴に関連した部分で水滸伝との関連性を述べていますが、オリジナリティと言う意味で馬琴より綾足を評価しています。やっぱり天下に名だたる博識な方ですなぁ、幸田露伴先生。 |
| 図説中国古代 戦争戦具 同済大学出版社 |
| 陸敬厳氏著。子供向けに書かれた中国古代の武具防具その他兵器のほぼA4サイズ140ページほどの図解集です。安かったんで、参考になるかと思って買ったんだけど、思いのほか良いかもです。写真、影印がもの凄く多いし、解説文も絵と半々くらい。水滸の話が出てる箇所もいくつかあります。日本で言えば、新紀元社の『武器と防具 中国編』のようなものだけど、流石に書いてる方が専門家且つ本家本元、敵いませんな。 |
| 洛神の賦 中国文学論文と随筆 武蔵野書院 |
| 目加田誠氏著。昭和四十一年発行の論文集。確か講談社学術文庫にもなってた筈。『水滸伝』関係は「水滸伝の解釈」と「滝沢馬琴と水滸伝」の二つ。前者は1950年代の水滸伝研究の概説で、中国での話がメインだけど、あの頃の中国の政治情況が色濃く出てて中々面白いっす。後者は割とさらっとした文章で、『新編水滸画傳』『南総里見八犬伝』の中から『水滸伝』に言及した箇所から考察して、馬琴の水滸感を検証してます。 |
| 中国人の面子2 はまの出版 |
| 江河海氏著/佐藤嘉江子氏訳。タイトル通り、「中国人の面子とは何か」「中国人にとって如何に面子が重要か」「中国人は如何に面子に縛られているか」を『水滸伝』『三国志演義』『紅楼夢』を例にとって、これでかこれでもかと解説してます。訳の問題なのか、時々「ん?」と言うところもないではないかな。でも、日本人の感覚からすると多少「???」と思うような箇所って『水滸伝』の中でもあるし、TVで中国の似非超能力者とか謎の気功師とか見ても「???」と思うことって多かったんだけど、これに書かれていることがいくらか誇張はあるにしても、中国人一般に普遍的なものだとすれば、凄く納得がいったりします。そう言う意味では、現在ビジネス等で中国の方とお付き合いのある方は参考になるかも知れません。こう言う中国人が書いた”文化論”って初めてだったんで、割と面白く読めました、はい。 |
| 中国ペガソス列伝 日本文芸社 |
| 中野美代子氏著。中野さんと言えば『西遊記』関係で有名な方ですが、これは『西遊記』関係なし。武則天・楊貴妃・西太后・三国志演義・水滸伝・フビライ・魯迅などについて書かれた文集です。『水滸伝』関係は、「盗賊の美学」と題された一章で、『水滸伝』と史実の異民族支配との関係をメインで論じています。16ページ程の章なんで、それほど突っ込んだ内容でもないかな?寧ろ、『水滸伝』以外の章が面白いっす。面白いんだけどさぁ、なんかなぁ...『水滸伝』の章の結びの一文がね、「私は、この小説を好まない。」って、わざわざ書かなくても...本編とは関係ないし... |
| 中国の名酒一〇〇選 徳間書店 |
| 今戸榮一氏著。はい、中国のお酒の本です〜♪前半はお酒の歴史、小説でのエピソード等々、後半は実際の名酒の解説になってます。この前半に、「『水滸伝』と酒の話」として一章が割かれてます。内容的には『水滸伝』中の酒にまつわるエトセトラなんで、当然メインは武松と魯智深(笑)滄州のお酒の所で、林教頭の話も出てきます。他にもちょくちょく出てきますな、『水滸伝』(笑)そう、この方は光栄の『新・水滸伝』訳した方なんで、きっと『水滸伝』好きなんでしょうな。寨主的にこれを”お勧め”せずに、何としようぞ(爆) |
| ドラゴンの系譜 福武書店 |
| 海野弘氏著。中国の過去から現代に連綿として続く秘密結社について書かれた本です。で、『水滸伝』も一章割いて語られてますし、実在の秘密結社と水滸の微かな関連性も僅かながら書かれてます。まぁ、それはさておき、時の権力に反抗し、自由を求める集団であった筈の秘密結社が、近代以降政治的ステージを与えられなくなった途端に反動的犯罪的集団に墜ちて行ったと言うことすらも、新たなる自由を求める中国民衆の伝統の一形態であるとする著者の意見、なんとな〜く肯けるものがありますな。で、話は変わるんですが、梁山泊も秘密結社なのかな?あんなに公然とやってるけど...寨主的には、もっとこう...例えば、ショッカーとか死ね死ね団とか...(汗) |
| 支那小説戯曲小史 東華堂 |
| 笹川種郎氏著。国会図書館のデジタルライブラリ蔵書。元代以降の小説戯曲についての概説ものなんですが、この中に「『水滸傳』及び『三國誌』」と題されて一章が割かれています。が、99%が『水滸伝』で残り1%が『三国志』、しかも『三国志』の評価たるや、けちょんけちょんもいいところです(汗)それに引き替え、『水滸伝』については魯智深関連の原文を挙げて、諸手放しで大絶賛してます。この本書いた方、実は笹川臨風さんでして、水滸の訳本も出されています。それもあるんでしょうが、それにしても『水滸伝』と『三国志』の落差激しいですな(汗) |
| 忠義水滸傳解 浪華書林 |
| 陶山南涛著。宝暦七年刊の本なんですが、賢弟犬大将殿からコピーを送っていただきました。『水滸伝』そのものではなくて、使われている字句の辞書です。江戸期は鎖国をしてたので、中国語会話を覚えようと思ったら、話し言葉で書かれた『水滸伝』はテキストとしては打って付けなわけでして、これもそう言う意図で出版されたものの一つです。高島先生の『水滸伝と日本人』によれば、陶山南涛と言う人はかなりハイレベルな唐話学者だったようですが、残念ながら私にはわかりません(^^;内容は漢文の序と自序、凡例、第一回から第十六回までの字句解説です。字句にはカナで発音が付けられていて、その後に意味解説となっています。当たり前ですけど、今の中国語と同じものもあったりして、結構今でも使えたりするかも(笑)それはともかく、なるほどなぁと思うことが多くって、思いの外楽しめたりするので驚きます。確か、汲古書院の『唐話辞書類集』のどれかにも影印が採録されていた筈なので、機会があれば昔の人のお勉強の後を偲ぶのも一興かと思うですよ。 |
| 春宵読本 文泉堂 |
| 泉鏡花著。これも国会図書館デジタルライブラリ所蔵っす(^^;明治42年刊のエッセイ集のような本です。かの有名な鏡花の本ですが、この中に「かながき水滸傳」と題するものがあります。この『かながき水滸傳』は江戸期に出された『水滸傳』の一つなんですが、『偐紫田舎源氏』を書いた柳亭種彦を含む何人かで書き継いだ本で、種彦が書いたところ以外はえらく評判の悪いです(笑)で、これは鏡花先生がこの本を火桶に凭れて読みながら、思ったことを書いた簡単な書評です。「火桶に凭れながら」ってところがポイントでして、真剣に読んで書いたもんじゃないってわけです(笑)内容的にはいくつか本文を挙げて、「種彦は巧いけど他はダメダメじゃん」と言っているようなものです(笑)ちなみに、頁にして10頁くらいの短い文章です。 |
| 僕たちの好きな水滸伝 宝島社 |
| 皆で著(笑)遂に遂に出ました、僕水プロジェクトの成果(笑)犬大将さん、笠原慎太郎さん、よんたいさん、食い倒れ梅吉さん、アジナーさん、大熊さん、よろずねこさん、あかねさん、井上浩一さん、月岡駿太郎さん、運福さん、紫夜藍さん、郭図さんら、イケイケの水滸関連サイトマスタさんたちと書いた他人の財布で出した同人誌(爆)いやしかし、結構大変だったのよ、期間短かったし。外字やら校正やら表記統一やら、出来る限りはやったんだけど...が、製版時点でぼろぼろにされたらどーにもなりまへん(笑)ま、それはともかく、ストーリー、好漢紹介、コラムとなかなかまとまってはおります。正子さん森下さんのインタビューも良いし。敢えて気に入らないところには言及しない辺りがなんですが(笑)コラムは通して読んでみると、書き手が違うだけにちょっと他の類似本にはない異色のテーマで面白いっすよ。いやいや、将に『水滸馬鹿どもが夢の跡』だ(笑)当然、お宝ってことで(笑) |
| 図解雑学 水滸伝 ナツメ社 |
| 松村昂・小松謙著本の安直なタイトルで馬鹿にしてましたが、はっきり言って日本の水滸サイトの危機です。この本、記載されてる内容、量、幅、どれを取ってもサイトのコンテンツとして文句なし、書いてる人は所謂専門家、この本で初めて目にする話もあり、値段もお手頃、文章も硬くなく判りやすく...つまり、完璧です(汗)一体、この本を読んで、私を含めた何人の水滸サイトマスタの更新意欲が削がれるか、それが心配...但し、”図解”の部分は図解ってほど図解じゃないっす。てか、図解って何? |
| 中国の歴史07 中国思想と宗教の奔流 宋朝 講談社 |
| 小島毅著全12巻の中国史シリーズのうちの一冊、宋の巻です。歴史の本なので、中央公論社や集英社の同様のシリーズと内容的には似ています。当たり前ですが(笑)遼・金等は別の巻なので、そこら辺りがないのは仕方がないすね。ただ、文化関係に割かれているページが他の本に比べると多いので、これはこれで面白いです。全体的に読みやすいし、良い本だと思います。 |
| 支那小説訳解 東海義塾 |
| 馬場譲得閲。これも国会図書館デジタルライブラリ。明治31〜33年刊の何だろう?例言を見る限り、メジャーな小説その他に訓点と語句解説を付けて、日本の小説を読む如くにしたよ、と書いてはありますが、どれもさわりだけなので、正直何を目的にしたものか不明。 一番近いのは教科書かな?でも、商業出版してるみたいだし... 内容は、遊仙窟・水滸伝・西遊記・照世盃・海外奇談・西廂記・三国志演義・杜騙新書・小説精言・李娃伝が入っていて、『水滸伝』は井上碩田と言う方の担当っす。馬場譲得閲ってのは、偉い先生がチェックしたよんと言うことで、実際書いてるのは先生じゃないって良くあるパターン。 『水滸伝』は『出像評点忠義水滸全伝』が底本の様子。引首から第二回の途中まで、原文に訓点と送り仮名を施して、その後に語句解説が結構丁寧に入ってます。と言うか、もの凄く充実してるっす。原文に対して、最低でも2〜3倍の解説の量っすね。 しかも、解説も結構面白い。文章がでなくて、書かれている内容が。これで120回やったらキツいだろうけど、個人的には頑張って欲しかったす(笑) |
| 支那小説戯曲文抄釈 早稲田大学出版部 |
| 宮崎繁吉著。これも国会図書館デジタルライブラリ。明治40年刊の口語文の本です。これは多分ですけど、早稲田大学の教科書っすね。最初に講義と合わせて読んでおけと書いてあるし。この方、号を來城と言って、森槐南の弟子だったようです。日本・中国・台湾を流離った漢詩人で、漢籍の翻訳等もやってたみたい。後に早稲田大学で教鞭も取っていたんですね、きっと。さてこの本ですが、内容は水滸伝・西廂記・桃花扇・紅楼夢の解題&訓点送り仮名&語句解説&意訳となってます。『支那小説訳解』と似た感じっす。『水滸伝』で取り上げてるのは第三回「趙員外重修文殊院 魯智深大鬧五臺山」の中の魯智深出家から二度目の大暴れが治まった辺りまで。 |
| 水滸伝 最強の豪傑は誰だ!? 茜新社 |
| 森下翠著。所謂コンビニ本なんすけど、よくぞ出版した(笑)ま、内容は森下さんなんで安心と言うか、絵巻の簡易版って感じ。いや、寧ろ光栄の好漢FILEをグレードアップした、と言うべきかも。もしくは一人『僕水』(笑)そして、近頃の原典知らない北方から入った人には打って付けの入門書と言えましょう。だってさ、値段500円だよ(@_@) |