道之巻
おまけとして、泊軍の使用した陣形の想像図を少し載せておきます。
まぁ、あくまで想像ですので、イメージがちっとでも涌いていただければよろしいかと思いまして...(汗)
実際にその陣形に効果的意味があるかないかは、お気になされないように(笑)

九宮八卦陣
さて、梁山泊軍の陣形と言えば最初に思い浮かぶのがこれでしょう。
私思いますに、公明哥々も呉用殿も陣形についてはほとんどご存じではありませんから、この陣形はかの九天玄女娘々から賜りました天書に載っていた陣形ではないかと考えております。
その謂いは、恐らく外陣と内陣(中軍)合わせて九陣を”九宮”、外陣の布陣位置が中軍から見て八方位に相当することから”八卦”、それで「九宮八卦陣」と呼ばれるのではないかと思われます。何で東西南北を震陣・兌陣・離陣・坎陣としないのかは謎ですね。まぁ、どうせなら四神を当てた方がインパクトがあるからかも知れませんけど。四神は東西南北の守護神でもありますからね。
で、私は天書を拝見できませんので、呉用殿の布陣が正しいのかどうかは判定できません。ですので、二つほど載せておきます。
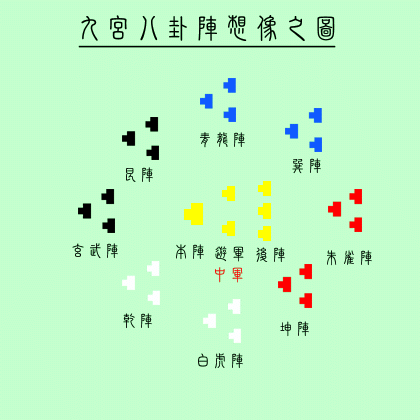
こちらは九宮八卦陣が円陣系だと仮定した場合の想像図です。
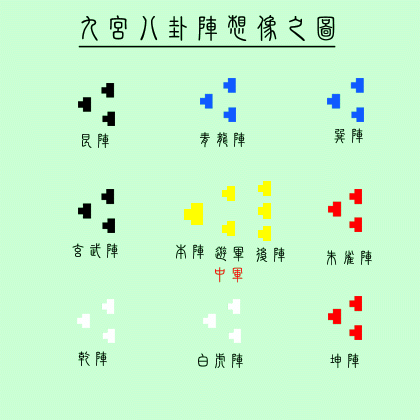
こちらは九宮八卦陣が方陣系だと仮定した場合の想像図です。
いずれにしても、中軍を中心に八方位に陣を構えた物で、上記は両方とも北方に敵が布陣している場合を想定しております。敵の布陣方向が違った場合は、基本的に各陣の相対的な位置は変えずに各陣ごとに敵に対して正面に向かって布陣することになるでしょうな。
円陣系は防御に適した陣形と言えますし、上記のことを考えると全方位に対して同一の防御効果があることから挙げてみました。
方陣系は『李衛公問対』などによれば陣形の基本で、李靖はかの諸葛孔明の「八陣図」も方陣であると言っています。李靖の「六花陣」もそれに倣って外陣が方陣で、中軍が円陣となっています。「八陣図」は「八卦陣」なんて呼ばれることもあるようですので、だとすれば九宮八卦陣はこれと同じ物である可能性もありますので、方陣としても挙げてみました。でも、「八陣図」は六十四陣から成るとも言われてますから、そうだと違いますね。
実際に使用した対童貫戦の時は、中軍の布陣は細かい陣の集合体ですけども、陣形自体で考えるには枝葉のことなので省きました。それに、中軍の構成は対遼戦などでも分かるように変わりますしね。
対呼延灼戦の布陣
呼延灼殿が梁山泊を攻めた時に泊軍がとった陣形が下の布陣図です。これは公明哥々の指揮で布かれた陣ですが、倭国では”車掛かり”と言われているようですな。武田信玄vs上杉謙信の第四次川中島戦で上杉軍の取ったのが”車掛かり”だと『甲陽軍鑑』にあります。
図で分かるように前軍を五陣に分け、一隊が闘ったら次ぎの隊に変わると言うように車の車輪のように敵と接触する陣がぐるぐる入れ替わると言うものです。
この時は、結局呼延灼殿の連環馬軍に敗れてしまいましたけど、それは陣形の問題と言うよりも軍装の問題ですね。
攻撃主体の陣形ですから、側面がちょっと不安ですね。敵の別働隊に横槍を付けられた場合、後詰めの左軍右軍が上手く対応しないと、前軍が分断されて各個撃破される危険があるかも知れません。
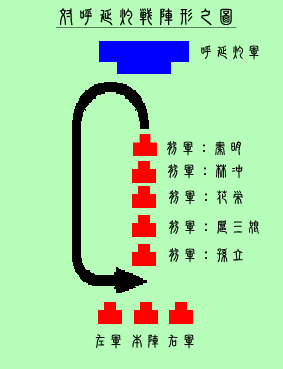
取り敢えず、こんな感じで(笑)

![]()
![]()
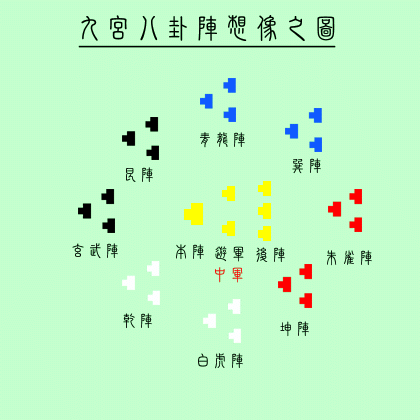
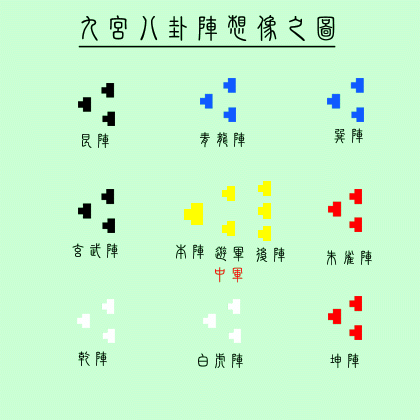
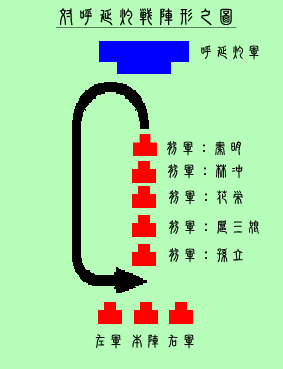
![]()