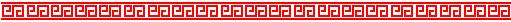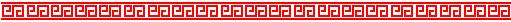
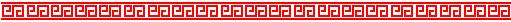
| 水滸伝 講談社 |
| 全八巻。駒田信二氏訳。百二十回本。完訳本として最初に読んだ水滸伝です。訳本の中では一番好き。なんでも文庫は絶版になったとか...残念です。宋代の官吏の職名とか、固有名詞を無理に訳さないところが原作の情緒を伝えている名訳ですね。これは文庫だけどもう絶版なので、新刊で買うなら平凡社の奇書シリーズかな?古本でも文庫はほとんど出ないけど、平凡社版は何種類かあって何件か古本屋さんを歩けば必ずと言っていいほどあるよ〜 |
| 水滸伝 岩波書店 |
| 全十巻。吉川幸次郎氏・清水茂氏訳。百回本。昔からあったんですけど、最近清水茂氏が改訳改版して新規に出てます。昔はちょっと違和感があったんですけど、今読むとそうでもないです。現在、文庫で十巻まで揃って出版されてます。 |
| ザ・水滸伝 第三書館 |
| 全1巻。村上知行氏訳。七十一回本。社会思想社版全5巻が在庫なしのため、やむなくこちらに切り替えました。紙質は悪いが、値段は安い。ノリ的には村上元三の「次郎長三国志」みたいだが(ちょっと違うかな?)、趣きあり。これと内容の同じ、教養文庫版もあります。 |
| 水滸傳 修道社 |
| 全9巻。村上知行氏訳。七十一回本。上の本や教養文庫の本と内容は同じなんだけど、昭和31年発行で新書版サイズのそれの最初のもの。ただ、巻一の巻頭にご本人の序があるし、序章が7回の後(第1巻の最後)に置かれていたりの違いはあります。それから、私好みのざっくりした画調の福田貂太郎さんと言う人の挿し絵があります。河出本や角川本にも同じ挿し絵があるのかな?この本の面白いところは、タイトルに「新中國定本普及版」と冠されていることです。最初にこの訳出した時は、ちゃんと間違えないように『金聖嘆本の訳じゃないよ〜』と明記してたんですね(笑) |
| 水滸伝 河出書房 |
| 全3巻。村上知行氏訳。七十一回本。遂に制覇しました、村上版(爆)もう、中身は読まなくっても同じだと分かってます(笑)新橋の古本市で初めてお目に掛ったんだけど、帯に”カラー版”と書いてある!?と、言うことは挿し絵が違う?で、買ってみたら違いました、挿し絵。これの挿し絵は川上尉平さんと言う方が書かれていて、カラーと白黒が半々です。この絵も中々好いんだ、また(笑)もしかして、私ったら水滸の絵だったら何でもいいのかも(爆)ん〜、否定できない...ご本人の書かれた解説と角川版にも付いてる120回本の大尾が終りにあります。修道社版は九巻が無いので、この解説が同じかどうかは分かりません。 |
| 水滸伝 角川書店 |
| 全4巻。村上知行氏訳。七十一回本。上記3種類と同じ訳で昭和48年の再版です。教養文庫版も持ってるから同じ訳で4種類目...なんで買ったか?挿し絵が井上洋介氏なんです、しかも各回毎に1枚で計70枚。あの絵好きなんだなぁ。で、下の講談社版の同氏の絵とは全然場面が違うんです。更に帯にこうあります。「『水滸伝』ついに日本テレビに登場!(開局20周年番組として10月初旬より放映)」どっちかってぇと、これに騙されたと言えなくもない... |
| 水滸伝 講談社 |
| 全1巻。七十回本?立間祥介氏訳。青い鳥文庫と言って、小学校上学年向きシリーズ。漢字には全部ルビが付いてます。子供向けのため、男女の場面はさらりと流してあるが、黄文炳は切り刻んで焼いて食われていた。PTAが...挿し絵は井上洋介氏。 |
| ものがたり水滸伝 朝日新聞社 |
| 全1巻。七十回本陳舜臣氏訳。1冊で余す所無く水滸伝を語ってます。ちゃんと全好漢が出演している辺りはさすが。合間々々に入っている解説が結構参考になってGood! |
| 反逆者の群像 水滸伝 日中出版 |
| 荒木猛氏訳?著?。解説と抄訳と完訳部分が渾然一体となった、ちょっと変わった内容の本です。140ページ程の薄い本で、「水滸伝とはこんな本」と言う紹介を趣旨としているようです。 |
| 新・水滸伝 光栄 |
| 全五巻。今戸栄一氏訳編。これ、普通の水滸伝じゃなくて、今世紀初頭から四十年掛けて書かれたものが底本です。(原題は水滸新伝)だから内容は大分違うんだけど、そう言うことを考えずに読めば十分面白いです。 |
| 水滸後伝 秀英書房 |
| 寺尾善雄氏訳。読んで字のごとく、その後の水滸伝の顛末記。生き残った好漢が李俊をシャム国の王様にしてハッピーエンドを迎えます。東洋文庫から水滸後伝の完訳が出てるけど、これは抄訳。わたしが買ったのは’94出版のものですが、もっと古いものもあります。内容は同じです。 |
| 水滸後伝 平凡社 |
| 寺尾善雄氏訳。遂に見つけた東洋文庫の完訳版。抄訳に比べると詩等もカットされていないので、より本編水滸伝の雰囲気を継承しています。いろんな本でも言われていることだけど、確かに水滸後伝はそれだけで読んでも完成された名作だ。水滸ファンなら一度は読むことを太鼓判付きでお薦めします。 |
| 水滸伝 金聖嘆 集英社 |
| 佐藤一郎氏訳。同じ集英社の世界文学全集でもこちらはデュエット版と言うようです。もう一つの佐藤氏訳「水滸伝」と同じものだと思って比べたら、あちらは完訳で、こちらは完訳から冗長部分を切り捨ててまとめ直したもののようです。所謂、抄訳に当るのかなぁ?とは言うものの、普通完訳と言うと”完”にこだわり過ぎて、現代日本語としては文法的に無理があるような訳を見掛けますが、そう言う意味ではこの本は文章を読んでいても違和感を感じることがありません。良訳と言えましょう。 |
| 水滸伝 金聖嘆 集英社 |
| 佐藤一郎氏訳。同じ集英社の世界文学全集だけど、上の完訳版。厚さ5CMなんで、ちょっと通勤途中じゃあ読めない。多分、デュエット版の元になっているので、訳自体は大変読みやすいですね。デュエット版との違いは完訳であること以外に間に国芳のカラーの水滸画が入っていること。 |
| 水滸傳 新制社 |
| 魚返善雄氏訳。教養文庫「水滸伝物語」と内容は同じのちょっと古いものです。私が知ってる中で最も短い抄訳かな。金聖嘆の七十回本が底本だから、これだけ260頁程度に収まったとも言えるけど、それにしても簡約だ。盧俊義の夢で終わるところもちゃんとあります。が、この本の特色はなんと言っても渾名まで訳したことでしょう。しかもこれがまた珍訳で、相当笑えます。最初に読む訳本としては薦められないけど、二冊目以降に読む分には超お薦め。 |
| 標注訓訳水滸傳 近世漢文学会 |
| 全15巻。平岡龍城氏訳。とうとう買ってしまった和装本。高島先生も書いていらしたけど、こりゃすげぇ。大正五年の本で、底本は金聖嘆の第五才子書。原文に返り点と送りがなが付いてて、左側に読み下し文、上に注釈があるところは漢文の教科書みたい。漢文を見慣れていない人にはちと辛いかな。龍城先生曰く、「金聖嘆の評が面白いのが判ればよい」と言うことで、15巻の終りに「読第五才子書法」と「第五才子書序」の訓訳が付いています。これ全部で9,800円は安いと思うのは私だけかな? |
| 國譯漢文大成 宣和遺事 東洋文化協会 |
| 全1巻。昭和31年の復版の方です。宣和遺事の他に「セン燈新話」「セン燈余話」と二つの伝奇文学が収められています。どうしても宣和遺事が読みたくて茅ヶ崎の図書館に行ったら、「そんなものはない」と言われて買ってしまいました。水滸伝の元となったと言われている宣和遺事ですが、実際は水滸伝関連部分は少しだけです。訳文自体が文語体のため、普通はちょっと読むのもしんどいかも。なので、ちょっとずつですけど、現代語に訳して公開します。期待しないで(汗)平凡社の「中国古典文学全集」の第七巻にも訳があるらしいので、興味のある方はそちらを探すのもいいでしょう。 |
| 水滸伝 岩波書店 |
| 全3巻。松枝茂夫氏編訳。40年程前が初版の岩波少年文庫の水滸伝で百二十回本ベース。第七十回までに比べるとそれ以降はかなり端折った抄訳になっています。少年向けと言うことでエログロ部分はうまく丸めて書かれています。質量共に最初に読むには良い訳本だと思います。最後の解説の中に、七十回本の盧俊義の夢オチの部分の訳が載せられている辺りも好感が持てます。内容が同じで上下2冊の昭和37年3刷のものも買ってしまった... |
| 中国古典文学全集 7 平凡社 |
| 京王デパートの古本市で、偶然見つけた本です。「京本通俗小説」「雨窓き枕集」「清平山堂話本」といっしょに「大宋宣和遺事」の訳が収められていますが、原文はありません。國譯漢文大成よりは遙かに読みやすいです。ちなみにこれも昭和31年出版で、すごく装幀の綺麗な本です。現代語訳の参考にさせて貰います。 |
| Outraws of the Marsh 北京外文出版社 |
| 全3冊。Sidney Shapiro氏訳。高島俊男氏の「水滸伝と日本人」にある通り、七十回本と百回本両方が底本みたいですけど、私には判らない...英語判らないし...目次だと百回まであります。今までは読んだ物しか載せてなかったんですけど、これは読むのに何年懸かるか不明なので、もう載せておきます(汗)しかし、中国の古典を英人だか米人だかが英訳して中国で出版した本が、イギリスの本屋を経由して私の家にあると言うだけでなんか感動してしまうなぁ... |
| 水滸伝物語 新潮社 |
| 大町桂月氏訳。本には”著”とありますが、内容的には原作に忠実な抄訳なので訳本と言ってもいいでしょう。四十九章で招安までで、最後に東征西伐して十八人は出世したが、残りは各地で戦死したと閉められています。大正八年の本ですが、文章自体は文語体です。但し、大正以前の文語に比べると簡単な文語だし(辞書不要なくらい)、漢字にはふりがなが付いているので(当然旧かなづかいだけど)、高校の古文程度の知識があれば十分読めると思います。文語故の格調の高さはそれはそれで味があって良いんですが、元々白話(話し言葉)小説の水滸伝を文語(書き言葉)訳にすると別のお話みたい、と言うのが感想かな。 |
| 水滸傳 第一書房 |
| 弓舘芳夫氏訳。昭和15年出版で、「戦時体制版」とあります。紙の質は悪いし、装幀も良くないけど、いや、こりゃ面白い。ちょっと訳本でこれだけ面白い本にはお目に掛ったことがありませんね。”ですます調”だったり、新聞調だったり、体言止めだったり、文体はいろいろなんですが、それが却って調子良いんですな。合間に入る軽い感想とか、外来語を使ったりとか、実に読者を飽きさせません。しかも挿し絵は小杉放庵、もしこの本が再版されるならば、私の一押し間違いなし。ただ、惜しむらくは、”紀元二千六百年三月”とはしがきにありますから、再版される可能性はまずありません。そう言う時代の本なので、当然旧字に旧仮名遣いです。いやー、是非読んでもらいたいなぁ... |
| 水滸後傳 天一出版社 |
| 上下二冊。民国六十四年初版とあるから、1975年に台湾で出た本です。所謂”影印本”で底本を写真に撮って出版したものですね。前記によれば、国立台湾大学図書館蔵の清乾隆三十五年(1770)の本が底本です。面白いのは、目録(目次)の前に朱書きで「天保四年に黄金一片白金両匹で買った、平山高知氏の蔵書」と書かれている所です。そのあと、この書籍がどういう経路で誰に渡ったかが書かれていますが、この本、日本にあった本なんですね。しかも、最初に出てくる高知平山と言う人は、高島先生の『水滸伝と日本人』によると文政十二年(1829)に水滸伝の訓訳を出している学者だった人みたい。でも、これは買った後に気が付いたのでした。実は、本を開いたら影印本だったんで、衝動買いしたのでした(汗)また、ろくに読めない本買っちゃった... |
| 后水滸伝 春風文芸出版社 |
| 1981年刊の中文書籍の排印本(活字印刷の本)です。その名の通り水滸伝の続編ですが、底本は作者不明で明末清初の頃の本みたいです。水滸伝の好漢は燕青しか出てこない様子で、登場人物たちは水滸伝の登場人物の転生と言う設定のようですね。でも、一〇八人はいません。それと四姦も転生してます(笑)で、最後は岳飛に退治されちゃうみたい。みたいと言うのは、ちゃんと読めないからなんですねー(笑)悔しいから、これもそのうち訳すぞー(本当か?) |
| 世界名作全集5 紅楼夢水滸伝 平凡社 |
| 松枝茂夫氏・駒田信二氏訳。昭和36年刊の本です。どちらも抄訳で、紅楼夢が松枝氏、水滸伝が駒田氏の訳になります。が、この駒田氏訳水滸伝、同じ平凡社ですけど百二十回本の抄訳ではありません。あとがきにご本人が「七十一回」本の訳だと書いています!だから、夢オチもありません。全集のラインナップを見る限り中学か高校生向けくらいのようなんだけど、食人場面も濡れ場もあるので大人向けなのか?文庫サイズで厚さ3cmハードカバーと言う外観も含めて、なんだか不思議な一冊ですね。 |
| 新譯水滸傳 中央公論社 |
| 全12巻予定で、9巻で中断。佐藤春夫氏訳(実体:村上知行氏訳?)。昭和27〜28年刊の本で、百二十回本の完訳です。残念ながら、1巻はないです。何故か遼征伐以降の部分は出版されなかったらしいので、1巻があっても半端ではあるんですが...村上知行氏が訳して佐藤氏の名前で出したと言うことですが、中身を読むと肯けます。何故って、『次郎長三国志』みたいな調子だから(笑)挿し絵は小杉放庵氏で、中々良いです。この本に大きめの栞が入ってるんですけど、それの表に佐藤氏のその巻に対するコメント、裏に村上氏が「註外の註 鶏のあばら」と題して読者の質問に答えていて、これが面白い!作中の言葉の解説とか、血縁関係とか内容は色々だけど、これを膨らませて本にしたら、さぞ面白いだろうと言う内容です。 |
| 第五才子書施耐庵水滸傳 中州古籍出版社 |
| 上下巻。金聖嘆評点の排印本中文書籍。金聖嘆評って言うのを見てみたくて買ってみました。残念ながら簡体字なので、ちょっと骨が折れるなぁ...でも、評自体は短いものも多いし、完訳本と中日辞典突き合わせで読めないこともない、筈だ(笑) |
| 水滸戯曲集 上海古籍出版社 |
| 全2巻。これも中文書籍で、元・明・清代の水滸関係の戯曲を21編集めた物です。これも、”水滸戯”って奴がどんなものなのか知りたくて買ってみました。所謂、”台本”なんで、こっちの方は難しいかも。まぁ、五年もあれば読めるでしょ(笑)先頭に明・清代に出版された水滸の戯曲本の影印が20頁くらいずつ載っています。 |
| 世界大衆文学全集 水滸傳 改造社 |
| 笹川臨風氏訳。昭和5年刊の本なので、口語訳ですけど旧仮名遣いです。武松が西門慶を殺して、孟州送りとなるところで終わってます。文庫本サイズのハードカバーで、頭に一枚史進対魯智深の絵があるだけで、挿し絵はありません。昭和初期の訳本と言うことで、言葉遣いが最近聞かない言い回しだったりします。なんか、亡くなったばあちゃんを思い出して懐かしい(笑)時々、古本市とかで見掛ける本ですね。 |
| 水滸伝 劇照挿図本 上海古籍出版社 |
| ”劇照挿図本”と言う響きに釣られて買った中文書籍です。が、頭に中央電子台水滸伝ビデオの写真が数頁あるのみで、中身は簡体字容与堂本でした(汗)そうと知っていれば買わなかったが、既に遅し...繁体字版容与堂本も注文していたのでした、しかも同じ出版社の(泣)ハードカバーの本ですけど、カバーの表紙の写真が無茶苦茶スプラッター...もうちょっと別の写真にすれば良いのに(滝汗)頭にある写真にコメントがあって、「征方臘」の写真の下に”一将功成万骨枯”とあるのは悲し過ぎる... |
| 容與堂本 水滸傳 上海古籍出版社 |
| 全二冊。と言うことでやってきた、繁体字版容与堂本です。縦書き繁体の排印本なんで、上の本とは比較にならないくらい、素人には読みやすい(って言ってもちゃんと読めないけど...)挿し絵もあるし、李卓吾の評もちゃんと載ってます。底本は北京図書館蔵の容與堂本だけど、缺頁缺字は日本の内閣文庫蔵容與堂本で補ってるんだって。これ二冊で二千円ちょいだから、中国の本って安いよね。まぁ、五十歳までには読めるようにしよう、うん(笑) |
| 新編水滸畫傳 有朋堂 |
| 全四巻。曲亭馬琴/高井蘭山訳。江戸時代の大ベストセラー。『新編水滸畫傳』読みたくてー読みたくてー、半年以上捜してやっと手に入れた、昭和二年刊の超美麗再版本です。以前の持ち主はよっぽど本を大切にする方だったみたい。挿し絵はご存じ葛飾北斎。この有朋堂文庫版も随分沢山挿し絵が入ってるけど、全部じゃないらしいです。馬琴&北斎だから、最強コンビと言ってもいいですな。でも、偏屈者の馬琴先生、本屋と喧嘩して初編巻之十までで辞めちゃいます。そこで、続きを訳したのが高井蘭山大先生。これねー、ちょっと文章が分かる人が読むと多分一目瞭然なんだけど、十回までは素晴らしいんだな、文章が。訳とは言え流石は馬琴先生で、興が乗ったら名文止まらずって感じ。巻初には用語解説や校定原本・編訳引書がちゃんと載せてあって、本文中の随所にも註が入っていて、これも中々詳しく書いてあります。ところが二編に入った途端に註の数が激減して、しかもたまにあるとしょーもねー註だったりします。で、二編の緒言で、蘭山大先生が続きを書くことになった経緯と岡島冠山先生の訳とされてる『通俗忠義水滸伝』やら原典やらの誤字誤訳をあーたらこーたら言ってるんだけど、訳文読んでみたら如何に蘭山大先生が似非野郎かが分かります。読んでて、「ん?」と思う所を原典で調べて見ると、ちゃんと書いてある所が抜けたり変わってたり。『通俗忠義水滸伝』見たら、全く同じ所がやっぱおかしい。で、付き合わせてみたけど、明らかに写してますな。共同出版の『忠義水滸伝』の巻頭に、そのことについてけちょんけちょんに蘭山大先生を非難してるけど、全く以ってご尤も。詳しくは高島先生の『水滸伝と日本人』をご覧あれかし。 |
| 繍像足本水滸傳 上海中央書店 |
| え〜と、民国25年ってことは1936年、日本で言うと昭和11年刊の中文書籍です。これ、背表紙が「繍像足本水滸傳」、表紙が「全像通俗小説 水滸全傳」、見開きが「倣古足本 繍像水滸全傳」、奥書が「全像水滸全傳」と全部タイトルが違います(笑)で、全伝となってますけども、内容は金聖嘆の七十回本の金聖嘆評抜き&金聖嘆自序付き&読第五才子書法付き&明の杜キンの水滸全図付き&見たことのない挿し絵の影印付きです。表紙の絵は獅子楼の武松VS西門慶で、これがまた如何にも中国チック(笑)字体は繁体字なんですけど、めっちゃくちゃ格好いい活字使ってます。で、標点符合はなし。ん〜、なんだか良く分かんないけど、すげー気に入ったから家宝に認定します(爆) |
| 世界名作選伝奇小説集 紫文閣 |
| 多摩松也氏訳ほか。昭和15年刊の旧仮名遣い口語訳の抄訳本です。見栄えは文庫サイズで箱入り、紙質は悪くて装幀らしきものは見えません(笑)一緒に「八犬伝」と「海の野獣」が入ってます。水滸伝は全部で149ページ、武松が孟州送りとなるところまで。ん?どっかで聞いたような感じ...そうです、笹川臨風訳と同じところまでですね。で、なんとなく気になって見てみたら、やっぱり笹川訳の名残がちらほら(笑)これ、”訳”となってますけど、笹川訳の”抄訳”だと断言します!原文は見てませんな、多摩さんって(汗)昭和15年は弓舘訳も出てるけど、このギャップはデカイ。ちなみにこの本、国会図書館にはありませぬ... |
| WATER MARGIN 香港商務印書館 |
| 全2冊。J.H.Jackson訳。香港で出版された金聖嘆七十回本の英訳本です。だから、夢オチもあります。時々誤植があって、渾名捜すの大変だった(汗)本当は私が生まれた年に出た本だけど、買ったのは最近出た再版です。綺麗なハードカバーの装幀で、つい見逃しそうだけど表紙開いたとこの紙に薄〜く好漢の渾名と名前が透かしてあって、中々の凝りようです。しっかし、英語にすると渾名が人によって全然違って面白いなぁ。これを以って確認されている英語の全訳3種類の渾名が揃いましたので、断金亭を見てみてね。 |
| 忠義水滸傳 共同出版 |
| 前後編。岡島冠山訳?買ってから一年も経ってやっと読み終わりました。だって明治四十年の本でぶっ壊れそうなんだもん(汗)巻頭に信夫恕軒(明治の文人かな?)の書いた再版序文、岡島冠山伝、『忠義水滸傳の刊行に就て』と題する冠山礼賛蘭山批判、それから前編後編にそれぞれ通俗忠義水滸傳と五才子書の挿し絵が1頁ずつ、新編水滸畫傳の北斎の絵が二十数枚付いてます。内容的には百回本で、江戸時代の本を校定して排印したものだから当然文語だけど、かなはひらがなです。で、これの原本が冠山訳かどうかについては高島先生の『水滸伝と日本人』に詳しく書かれてますが、私も冠山じゃないと思うなぁ。別に学術的な根拠がある分けじゃないけど、冠山って当時の中国語専門家(それも話言葉の)で水滸伝の和刻本も出してる人なのに、この本の内容は原典に比べてあまりに変な訳になってる箇所が頻繁にあるんです。素人の私が見ても分かるくらいだから、本当に冠山ならそんなことはしないだろうなぁ、と思うんですけど、どうかな? |
| 世界大衆文学名作選集 水滸傳 改造社 |
| 笹川臨風氏訳。昭和14年刊の本で、『世界大衆文学全集 水滸傳』の再版本です。だから中身は一緒。装幀がペーパーバックみたいな感じで紙質も悪くなってます。普及版なのかな?これも元の本と同じで挿し絵はありません。が、この安っぽい本の装幀を担当された方は清水崑さんで、創元社の奥野信太郎氏訳『世界少年少女文学全集 東洋編 水滸伝』の挿し絵を書かれた方です。まぁ、ここまでなら私も『ふ〜ん』なんだけど、その表紙の絵のタッチがあまりに違うんでよくよく見たら、小さい字で「未醒書ニヨル」と書いてある(汗)そうです、未醒さんって私が大好きな小杉放庵さんのことなんですねー。確かにどう見ても放庵タッチの絵です。で、悩んじゃった...清水さんが放庵さんの絵を真似て書いた絵なのか、放庵さんの絵をそのまま表紙の装幀で使って、装丁者としてサインだけ入れたのか...ん〜、謎は深まるばかり...んでんで、笑っちゃうのは、この本の本文は武松が孟州送りになる所までなのに、表紙のこの絵は『盧俊義史文恭を活捉にす』の場面なんですね〜(笑) |
| 世界文学全集20 水滸伝 研秀 |
| 駒田信二氏訳。のっけから何なんですが、謎の本です(笑)見た目で言うと、焦げ茶のビニールの表紙に金文字でタイトルがあるあたり、高校とかで使ってた辞書みたいな感じですな。で、奥書が一切ないんで何時出版されたのか、値段が幾らだったのか等は全く不明。恐らく一般書店で売ってた本じゃなくて、通販とかでセット売りしたモノだと思われます。で、訳者は駒田先生なんだけど、解説によると百二十回本の抄訳を中国にならって七十一回までで留めた内容です。つまり、夢オチはなし。かと言って、『世界名作全集5 紅楼夢水滸伝 平凡社』とは違う訳になってるので、この本用に訳し直したか、百二十回訳から編集し直したかしたようです。二段組で500頁超えた本ですので、抄訳とは言え、それなりにちゃんとしてます。更に挿し絵なんですが、金子三蔵って人が描いてるんだけど、これが...まぁ、見てみてください... |
| 中国古典シリーズ 水滸伝 朝日新聞社 |
| 上下巻。陳舜臣氏訳。1975年出版、ハードカバー箱入りで、横長のちょっと面白い本です。中身の文章は『ものがたり水滸伝』と同じものなんですが、挿し絵が...すんません、惚れました〜(笑)実は宮田雅之さんなんです、それも32枚!箱のも入れたら36枚か。宮田雅之さんと言えば有名な切り絵作家で、水滸伝の作品があるとは聞いていたんですけども、切り絵の作品群として存在するものだと思ってました。が、この本の挿し絵だったんですねー(喜)いや本当に良いんですよ〜、これが〜(喜)多分、宮田さんのお名前をご存じでない方も、絵を見れば『おっ、見たことある』と言う方が多いんじゃないかな?こーゆー出会いがあるから、水滸本買うの辞められないんだよなぁ(笑) |
| 水滸 人民文学出版社 |
| 上下巻。中文繁体字の七十一回本です。所謂、中国で一番メジャーなハッピーエンド水滸伝です。つまり、金聖嘆七十回本ベースで夢オチなしの「英雄排座次」まで、残虐シーンをソフトにして、宋江を百回本とか百二十回本みたいにもうちっとマシにしたと言う、中華人民共和国になってから編集しなおされたものです。だから当然、金聖嘆批評はないけど、その替りに古語とかの脚注が付いてます。でも、なんだか毛主席がどーしたこーしたとか、金聖嘆は反動的だとか、再版解説に中共の匂いがちらほら... |
| 少年少女新世界文学全集34 水滸伝三国志 講談社 |
| 七十回本立間祥介氏訳。昭和38年刊の講談社の子供向け全集の一冊です。私と同じ年生まれの本ですね(笑)三国志の方は駒田先生が訳されてます。講談社は昭和34年に『少年少女世界文学全集 東洋編(2) 三国志水滸伝柳斎志異』を出していますけど、また新たに子供向けの全集を出したんですね。だから、”新”なんでしょうな。こちらの監修には、川端康成氏が名前を列ねています。内容的には講談社「青い鳥文庫」の立間版と同じで、挿し絵は山崎百々雄氏と言う方。中々味のある挿し絵ですよ。ちなみにこちらは子供向けとは言え、原作に忠実な抄訳なので「訳本」扱いしています。 |
| 聖嘆外書水滸傳 青木嵩山堂 |
| 全四冊で七十回本の第十一回まで。平山高知訳。高島先生の『日本人と水滸伝』によれば、この本は文政12年刊(1829年)なんですが、奥書に出版社の東京支店の住所が”東京市”なんてあるところから、再版本のようです。しかし、どう見ても版木から刷った物としか思えない(汗)多分、明治初期の頃に大阪の書肆で出版した和装本じゃないかと。内容的には”通俗”でない訓訳本なので、原文に訓点とカタカナの送り仮名だけですが、金聖嘆注の部分も全て入っています。四冊目の最後に、語句辞典が付いています。一冊目だけはすごく虫が喰ってますが、数少ないちゃんとした本なので、お宝認定します(笑) |
| いてふ本新編水滸畫傳 三教書院 |
| 全六冊。『新編水滸畫傳』ですから、内容は馬琴先生&高井蘭山先生&葛飾北斎のものですが、この「いてふ本」と言うシリーズは面白い。昭和10年刊で、文庫本のような紙に排印して線装(糸綴じ)にしたもので、新書版より一回り大きな本です。私みたいな好事家向けの本かな?(笑)但し、六冊で中断しているので、百二十回本の第七十四回、李逵が知県に扮装するところまでです。 |
| 一百二十回的水滸 商務印書館 |
| 上下冊。中文繁体字の百二十回本です。楊定見本と言う奴ですね。巻首に『宣和遺事』の『水滸伝』の元になった部分の抜粋と百八人の好漢の出身及び職業が載っています。挿し絵等は一切ありません。これで中文原典は、七十回本・七十一回本・百回本・百二十回本と揃ったことになりますな。 |
| THE EVOLUTION OF A CHINESE NOVEL HARVARD UNIVERSITY PRESS |
| RICHARD GREGG IRWIN氏著/訳。1953年に発行された本の再版のようですが、教科書で使ってたみたいですね。英語の中に繁体字の漢字がちらほら挟まってるのって、なんかすげー違和感あるな(笑)それと、中国語の人名とか名詞は全部漢字で統一してくれりゃいいのに、英語表記(ピンインかな?)の所が多いので、なんだかよく判らなかったりする(滝汗)副題が『水滸傳』となっていて、史料等の説明、『宣和遺事』『元曲』からの成立過程、版本概説などが書かれています。英訳本の比較(バック訳とシャピロ訳)などもありますね。と、ここまでなら「水滸資料書房」入りだと思うでしょ?でもねぇ、これには百二十回本各回の抄訳が載ってるんですな。が、それだけじゃない!なーんと、『大宋宣和遺事』の水滸関連部分の英文完訳まで載ってるんですぜ(汗)まぁ、あちらの大学の中文の教科書だとしたら、別段驚くことじゃないかも知れませんが... |
| 新譯水滸全傳 至誠堂 |
| 上下冊。久保天随氏譯補。明治四十五年発行の文語訳百二十回本。が、第一回を七十回本みたいに”楔子”としているので第百十九回までしかありません。巻頭にいくつかの原典の序と『宋史』『宣和遺事』の関連部分の抜粋に訓点を振ったもの、それから叙説が付いています。それによると、冠山の『忠義水滸傳』は言葉足らずで、『新編水滸畫傳』は馬琴訳部分以外は前者の盗作でダメダメなんで、新たに百二十回本を訳そうと思ったけどチョットわけありのため、金聖嘆の七十回本とそれ以降は李卓吾の百二十回本を使ったとありますから、百十九回の理由も判りますな。文語訳だけど、少なくとも前に挙げた二書よりは良いと思いますよ。 |
| All Men Are Brothers The George Macy Companies,Inc. |
| Pearl S. Buck訳。1933年に出た金聖嘆七十回本パール・バック訳の1948年の再版本。A4サイズ厚さ5cmと大きな本です。英訳の善し悪しはさっぱり分かりませんが、Miguel Covarrubiasと言う人の描いたこの本の挿し絵は良いっす。白黒の小さい挿し絵もあるんですけど、丸々1ページ使ったカラー挿し絵が32枚入っていて、とっても綺麗。なんで、何枚か『孫新之酒肆』に挙げておきます。これで今の所確認されてる英訳は制覇しましたぞ〜(笑)高い本だと思いきや、米国のweb古書店で日本円にして約3,000円とはお買い得。 |
| 水滸伝(旧訳) 岩波書店 |
| 全十三巻。吉川幸次郎氏・清水茂氏訳。百回本。岩波文庫の旧訳です。今出てるのはこれの改訂版ですが、ほとんど別物と言っても過言ではありませぬ。なんて言えばいいんでしょう、兎に角日本語が強烈です(笑)それについては以前からいろんな人に指摘されてたようですが、なるほどさもありなん(笑)そう思いながら読むと、これほど面白い訳本もないかも知れません。どんな面白い日本語があるかは...できれば一度ご自分で確認されることをお勧めします(笑) |
| 新訂水滸傳 中央出版 |
| 幸田露伴校定。昭和四年刊の『新訳日本文学叢書』と言うシリーズの中の一冊です。ん?日本文学?そう、中身は『新編水滸画傳』です(笑)でも、「第三編巻之三十」まで。つまり、百二十回本の第三十三回まで。同じシリーズの中の『通俗三国志』は上中下三冊で完結してるのに、なんで『水滸傳』はこんな半端なんでしょう?謎です。構成は、最初に露伴の「題水滸傳」と言うさらっとした水滸の成立史みたいなもの、第一編目次、『新編水滸画傳』に付いてる「水滸序」、「譯水滸辨」、「職役稱呼俗解」、第一編の本編、露伴の「再題水滸傳」と言う『宋史』を引いた宋江の史実関係を述べたもの、第二編蘭山の書いた緒言、第二編目次、第二編の本編、露伴の「三たび水滸傳に題す」と言う「宋史」を引いた張叔夜について述べたもの、第三編目次、第三編の本編で、挿し絵は一切なし。編毎にページ振り直してるんで、同じページが三回出てきます(笑)露伴の名前は人寄せでしょうね、きっと。 |
| 中国の古典文学 水滸伝 さ・え・ら書房 |
| 杉本達夫氏/中村愿氏共訳。上下冊。1977年発行で、今でも出版されています。子供向け専門の出版社故に流石に息が長いです。おそらく小学校高学年向けに書かれたものかと思われます。ベースは七十一回本。2冊なので、細かいところは端折っているものの、ほぼ原典通りの比較的詳しい抄訳本だと言えす。渾名も訳しちゃうところは魚返版みたいですが、あそこまでブッ飛んでません(笑)きわどい描写のところもぎりぎりまで書いておいて、いよいよってところでさらっと流す、みごとな手際(笑)解説に簡単な百二十回本のあらすじが付いてます。子供向けとしては可もなし不可もなしってところです。 |
| The Water margin or The 108 Heroes Tynron Press Ltd |
| シンガポールで出版されたと思われる英訳本です。が、これってJ.H.JACKSONの『WATER MARGIN』から現代語訳且つ抄訳に編訳されたものとあるから70回本の筈なのに、なぜか夢オチなし(汗)とは言うものの、抄訳と言っても800ページもあって、各回毎の抄訳になってます。渾名等も結構変えられてますんで、また一興っす。李袞とかのピンインが全編間違ってるので、編訳とは言っても原典も見てるのかも知れません。ちなみに各回毎に新規に登場する好漢の挿し絵が各回の間にあるんですが、これは戴敦邦さんの『水滸人物壹百零捌図』の好漢図です。でも、どこにも書いてないし、よ〜く見ると非常に巧い人が模写していると思えなくもない(滝汗)否、多分そうだ...折角なんで、「鴨嘴灘」の「英訳渾名一覧」に追加しておきます。 |
| 絵本忠義水滸伝 |
| 明治十九年刊の再版本で、元は岡島冠山訳の『通俗忠義水滸傳』です。高島先生の『水滸伝と日本人』の「旧訳の再版」に出ている和解・出板人武田平治の洋装本で、口絵十枚だけが片面印刷袋綴じで大蘇芳年の彩色画、本文以降は両面印刷で挿絵は水野年方(大蘇芳年の弟子)のようです。本来上下巻ですが、買ったのは下巻のみ、呼延灼の梁山攻めから百二十回まで。但し、回立てではなくて巻の十七で完了となっています。ちなみに和解(和訳)とありますが、元が『通俗忠義水滸傳』なわけで、訳すも何もないと思うんだけど(汗) |
| 稗史水滸傳 |
| 文政十二年(1829年)から延々二十余年に渡って出版された本の大正六年刊の再版本で、山東京山・柳亭種彦・笠亭仙果・松亭金水の共訳です。共訳と言うと聞こえは良いけど、実態は出来が悪かったり、書くのが嫌んなっちゃて引き継いだりってことです(笑)和装排印本で、挿絵は歌川国芳、巻頭の絵だけは彩色手刷りです(驚)元々が合巻で絵本のように絵の空いているところに文章を書いた本ですが、排印にするため絵だけそのままで文章は削ってあります。で、各頁とも上に絵が下に文章があります。巻頭の解題にもありますが、山東京山は文章が下手糞で、メリハリのないのっぺりした文章ですが、柳亭種彦が書いたところは流石にリズムが良いですな。で、基本的に訳なんでしょうけど、結構原典と違う設定になってるところとか、多少違う展開になっちゃてるところがあるのはご愛敬なんでしょうね(笑)ちなみに「稗史」と書いて「よみほん」と読みます。 |
| 新譯水滸傳 日高有倫堂 |
| 伊藤銀月訳。これも国会図書館のデジタルライブラリです。明治41年刊の口語訳です。口語訳ですが、当時の本なので当然旧仮名遣いで漢字は旧字です。本書は四十回となっていますが、内容的には鴛鴦楼までなんで、原文の回とは一致しません。と言うか、最初は一致してたんだけど、林冲落草直後からいきなり猛ダッシュ(笑)智取生辰綱なんて、どこが智取だか読んでもさっぱり分からない(笑)でも、著者の名誉のために言っておくと、名文だと思いますです。エラく調子の良い文章なんですわ。と言うか、”訳”と呼んで良いか微妙と言う噂もあります(笑)でもでも、読んでて面白いのは確かです。これがタダで読めるのは貴重と言って良いでしょう。挿絵は小杉未醒(放庵)さんですが、ちょっと堅めの絵なんで弓舘氏訳の挿絵の方が良いかも。 |
| 新編水滸傳 一二三堂 |
| 曲亭馬琴・高井蘭山訳。更に国会図書館のデジタルライブラリです(笑)明治25年刊の『新編水滸畫傳』の再版本なので、本文的には特に言うべきこともありません。強いて言うなら、句読点なし段落なし古い活字なので今の人には読み難いってことかな?(笑)本来の『新編水滸畫傳』には、タイトル通りに北斎の多数の挿し絵がありますが、この本では北斎の挿し絵は割愛されています。ただ、巻頭に作者不明の21人分の好漢画が付いています。しかし、千三百四頁を一冊の本にしちゃうのはすごいなぁ...重くて読めないよ(笑) |
| 国譯漢文大成 水滸傳 国民文庫刊行会 |
| 幸田露伴訳。上中下巻。大正12年刊。120回本全訳なので、本文巻頭には『国譯忠義水滸全書』とあり、訳文のみで2200頁強あります。デカくて重くて、とても通勤電車で読めるようなシロモノじゃありません(笑)構成は、国譯忠義水滸全書解題、原書小引、李氏蔵本忠義水滸全書引首、訳文、原文となっていて、全部合わせると3000頁越えます。挿し絵はありません。訳文中に注がありますが、注の量はばらばらですね。内容は同じ文語訳と言っても、馬琴の『新編水滸畫傳』辺りとは大違いですね。まぁ、一般向けの読み物と言うよりも、学術出版的なものだと思うんでやむを得ないんでしょうが(汗)具体的には、露伴訳は漢文の読み下しだと思ってください。つまり、原文に訓点を振ったものをそのまま平易な日本語に訳さずに読み下した感じとでも言いましょうか。シリーズタイトルからしても、元々そう言う意図で制作されたものなんでしょう、同シリーズ中の『宣和遺事』も同じようなスタイルですし。まぁ、そう言ったわけで、最も難しい『水滸伝』と言っても過言ではないでしょうな。同時期に出版された平岡龍城の『標注訓訳水滸傳』の方が、同じように学術的ではありますが、より懇切丁寧で素敵です。でも、それは露伴の本がダメと言うよりも、龍城の本がスゴ過ぎると言うべきです、はい。 |
| 水滸傳物語 冨山房 |
| 高須梅渓訳。上下巻。まだまだ続く国会図書館のデジタルライブラリ(笑)明治36年刊の口語訳なんですが、普通の訳本とはちょっと違います。違うと言うか、抜粋抄訳とでも言えばいいのかな?「はしがき」には、『水滸伝』は長文でとてもじゃないが全部は無理なんで、魯智深武松をメインに宋江を絡めて、全体のストーリーがわかるようにまとめた旨の言い訳があります(笑)で、どうなっているか言うと、120回本の第三回〜第七回途中、第二十三回〜第二十九回、第三十五回途中〜第四十回、第五十五回〜第五十七回、第六十六回、第七十一回〜第七十三回、第七十四回途中〜第七十七回途中、第八十回途中〜第八十一回途中、以上の部分を前後に簡単なつなぎをくっつけて、それっぽくした抄訳だと思ってください(^_^;ちなみに、所々に挿し絵がありますが、これは『新編水滸畫傳』の北斎の絵ですね。 |
| Au bord de l'eau Gallimard |
| Jacques Dars訳。全2巻。酔虎寨初登場、1998年刊のフランス語完訳ペーパーバックの本です。見開きに「VERSION DE JIN SHENG-TAN」とありますので、70回本ですな。多くないけど、所々に容與堂本の挿し絵が入ってます。それから、各巻の最後に水滸伝上の中国地図と開封府の地図が付いてますが、ごっちゃごちゃで見難いっす。ま、漢字じゃないから仕方ないけど。で、内容ですが、聞かないで(笑)完訳だから、きっと同じだって(爆)後はドイツ語訳か...実は親父に言われました。「お前、フランス語読めないのに、そんなもん買ってどうすんだ?」自慢じゃないが、中国語だって英語だって、まともに読めないぜ(笑) |
| 新編水滸畫傳 集文館 |
| 全5巻。何度も登場の『新編水滸画伝』ですが、これは明治四十四年から大正二年に掛けて出版されたものです。内容的には巻之四十五、二仙山で李逵が羅真人を殺しに行くところまでです。北斎の挿絵はちょっとだけ。漢字にふりがなが付いてるけど、全部じゃなくてしかも難しい漢字ってわけではないので謎です(笑)五巻までしか出てないようですが、五巻目の最後の目録を見ると七巻まで載ってるから、もうちょっと続く予定だったみたいです。さてこの本、ここまではどうってことなくて、問題はここから。実はこの本シリーズ物で、「袖珍文庫」と銘打ってあって、文庫本より一回り小さい手帳サイズなんですな。ま、それしか取り柄がないとも言うんだけども(笑) |
| 物語近世文學 水滸伝 雄山閣 |
| 全2巻。シリーズ物の十二巻と十四巻です。昭和十六年刊の抄訳ですが、訳者は載ってません。巻頭に笹川臨風の解説が付いてます。挿絵はなし。全部で500ページほどだけど、百二十回本ベースで最後までなので、一回あたりに換算すれば4〜5ページって感じの抄訳だと思えば間違いなし。一応訳としては会話もあるんだけど、全体としてやけに素っ気ない文章で、これを最初に読んだら『水滸伝』ってつまらないと思っちゃうかも(^_^;まぁ、シリーズタイトルからして、名作の簡約ものっぽいので、それもやむなしかな。 |
| タイ語訳水滸伝 ※認定枠外 |
| よんたいさんから帰国オフの時に頂いたタイ語の抄訳水滸伝です。中国語、英語、フランス語と、ここまではどうにかこうにかアレでしたが、流石にタイ語は手が出ません(汗)なので、醉虎寨初ですが、タイトルすら判りません(笑)漢字と数字以外、一文字も読めません(きっぱり)と、言うことで、当然の帰結として認定枠外です。さぁ、どうとでもしやがれぃ(開き直り) |
| 評注図像五才子書 |
| 清の光緒丁未年とありますから、1907年刊の線装中文書籍。全巻揃いじゃありませんが、揃ってたとしてもそれほど貴重なもんじゃないのではなかろうかと。状態も悪いしね。幸い、一巻があるので、第五才子書の序から宋史綱、宋史目、読第五才子書法、原序までのセットは読めます。王望如先生評論出像水滸伝総論と評論出像水滸伝姓氏、肖像28枚が付いてるので、『醉耕堂本』が底本みたいっす。「倣泰西法石印」とあるのは何かね?ヨーロッパの石版印刷真似ました♪ってことかな?ま、いずれにしても、専門家でないのでさっぱり判らないと断言しておきませう(笑) |
| 日本輪王寺蔵水滸 武漢出版社 |
| 1994年刊の中文書籍。他のものと違い、文簡本になりますが、排印本なので挿絵部分は最初に16枚分のみっす。回数は百四回で、内容は征田虎・征王慶も入ってます。なので、120回本と同じっぽいんですが、かと言って同じではないっす。ま、内容がほぼ同じで回数が違うので、120回本と話の切れ目が違うし、その関係で回のタイトルが飛んでたり、後半になるとタイトルが別ものになったり、内容が変わってたりもします。底本は万歴22年福建で出版された『忠義水滸志伝評林』ですが、徳川家康のブレーンとして有名な南海坊天海の蔵書です。日光山輪王寺の住職だった関係ですね。 |
| 水滸後傳 庚寅新誌社 |
| 森槐南訳。全18冊。明治26年から18ヶ月掛けて毎月一冊づつ出版した完訳水滸後伝です。100年以上前の本ですね。”本”と言うより、雑誌に近い体裁ですね。紙質も良いとは言えません。一冊づつ買うより、事前予約で前払いの方が若干安くなる仕組みになっているんだけど、2冊目の最後に思ったより紙枚が増えて、当初より高くなったけど許してね、と広告が出てたり(笑)最初の方の巻の最後には、前巻の各新聞社等の書評が掲載されてるのが面白い。明治期の本ですので、全て文語と思いきや、会話部分は口語訳でそれ以外が文語と言う面白い訳になってます。しかも、会話はべらんめぇ調、それ以外の文語はちょい硬めの文語なので、更に面白い対比になってます(笑)森槐南と言う人は、明治期では結構メジャーな学者だったみたいですね。 |
| 新譯繪本水滸傳 左久良書房 |
| 小杉未醒訳/画。国会図書館近代デジタルライブラリ所蔵。明治44年刊の70回本抄訳です。訳も挿絵も小杉放庵さんです。最初に自序があるんですが、ここに「只一つ自分を信ずるものがある。それは自分が最も水滸傳を愛して居たと云ふ事だ」とあります。えぇ、認めますとも(笑)挿絵は本職ですから最高っす。108枚ありますけど、タッチが一律ではありません。場面々々にあったタッチの挿絵になってるんで、ちょっと見複数人で描いたかと思っちゃいます。デジタルなので判らないけど、挿絵のページの裏が白紙なのは挿絵が印刷じゃなくて木版画だからだそうで、驚いちゃいますね。明治期の本には時々手刷りの挿絵等が入ったものがありますが、これだけの枚数ってのは寨主が知ってる限りないです。訳は抄訳と言いましたが、エピソードの省略はありません。但し、流石に可もなく不可もなしって感じです。それでも底本に原典の五才子書を使い、冠山・馬琴も参考にして訳してるんですから大したもんです。この方は画家ですので、訳は本職じゃないんです、念のため。でもしかし、水滸本としては間違いなく上の部類です。保証します。 |
| 通俗水滸後傳 兎屋誠 |
| 村松操訳編。全8巻。国会図書館近代デジタルライブラリ所蔵。明治15年から18年に亘って出した本みたいですが、訳者他界により8巻18回までで途絶してます。挿絵は各回見開きで一枚、松斎吟光とありますので安達吟光が描いた錦絵風のものです。本の体裁はデジタルなのでよく判りませんが、版心があるので排印線装本だと思います。森槐南訳と違い全て文語訳ですが、漢字には読み仮名が振ってあるので、”字を追う”には助かるかも。ちなみに、「兎屋誠」と言うのは今で言う出版社ですが、屋号+名前だったりする辺りが時代を感じさせますね。 |
| 李卓吾批点忠義水滸傳 共同出版 |
| 2巻。国会図書館近代デジタルライブラリ所蔵。明治41年刊の本ですが、これは訳と言えば訳、原典と言えば原典です。なんとなれば、読む本と言うより多分学術書として出したものだと思うけど、原文に訓点振った本です。体裁は排印線装本で9回まで。平岡龍城さんの『標注訓訳水滸傳』と同じような感じですが、あっちを知ってるとインパクトに欠けるかも。でもまぁ、純学術的にどっちが優れてるかは、当然あたしにゃ語れない(笑)ちなみに訓点振った人の名前は書かれてません。 |
| 繪本通俗水滸傳 三新堂 |
| 桃川燕林口演/今村次郎速記。全8巻。国会図書館近代デジタルライブラリ所蔵。明治30年刊。表紙には『繪本通俗水滸傳』とありますが、中では『繪入通俗水滸傳』となってる所もあります。が、この本の面白いところはそんなもんじゃない。”口演”となってることからも判るかと思いますが、三新堂の主人が依頼して講談師桃川燕林に語らせ、それを速記して印刷出版した本なんですね。中国の『水滸伝』が元々講談から発展したことを考えると、いや中々乙な趣向と言うべきか(笑)講談故に原文には拘らなかったのか、始まりは竜虎山からじゃなくて、李吉が史進の家を覗いたところから、最後は招安なるところまで。800ページ以上のボリュームなんで、これを語るとなったら一体全体何時間掛かったのか、恐ろしくなりますな(汗)元々6巻の予定が収まらず、8巻になったのも宜なるべし。つか、水滸本の場合は良く聞きますが(笑)絵本と言っても、絵は各巻の頭に3〜4枚あるだけで、多分一鳳斎平沢国明と言う方かと思います。やっぱ、読むより聞きたいね、これは。 |
| 水滸傳物語 鈴木書店 |
| 伊藤銀月訳。これも国会図書館デジタルライブラリで、明治44年刊行の洋装本、訳文は文語文で漢字に全て読み仮名が振ってあります。途中に挿絵はなく、巻頭に3枚だけ。どこかで見た絵なんだけど、さっぱり思い出せない...一応100回本がベースだと思います。 一応と言うのは、招安の次に公孫勝が帰郷して征方臘へと続きます。征遼がないっす。 まぁ、元々抄訳なので、言い出したらキリはないんですが。 明治41年刊の伊藤銀月の『新譯水滸傳』はあれだけ良く出来た口語訳なのに、それから三年後のこの本は文語訳でしかも面白くないっす。 高島先生がおっしゃるように、きっと名前貸しで誰かが訳したんだと思われます。 |
| 通俗水滸後傳 由己社 |
| 九岐晰訳。号は竹外逸士。これも国会図書館デジタルライブラリ。明治15年刊の文語訳の本です。この方、えらく幅広い著述活動してた人みたいっすね。子供向けから主婦向け、果ては政治向きの本から小説、更に『通俗水滸後伝』の訳と何でもありっす(笑)デジタルライブラリにUPされているのは巻之一第二回までですが、目次上は巻之二十まであります。一冊で中断されたのかな?最初に好漢の顔絵が8人分、九岐晰の自序、原序があって、本文途中2枚ほど挿絵がありますが、日本人の描いたものではなさそうな感じ。通俗の文語だからそれほど難しくはないけど、特にかな文字の活字が古いものなので、例えば”に”が”尓”を崩したものだったり、慣れない人にはちと読み難いかもです。ま、この頃の本は口語訳の本でも活字に関しては同じなんですけどもね。 |
| 通俗忠義水滸傳 |
| 岡島冠山訳。何度も登場してますけど、冠山訳と言われている『通俗忠義水滸傳』の和本です。二・八・十二・十三・二十五・二十七・二十八巻だけですが、何しろ状態が悪くて奥付も無くなってるし、水に浸かったらしく、激しく染みてるので、何時の頃の本かさっぱり判りません。初版が250年くらい前なんで、それ以降明治までのどこか。ま、和本なんで当然版木から摺り起こすから、科学的な年代測定でもしなけりゃ判るわけないんだけどね。取り敢えず、洋装排印本はあるので、資料的価値として買ってみました。千円だけど(笑) |
| 水滸伝物語 実業之日本社 |
| 鈴木悦訳。これも国会図書館デジタルライブラリっす。大正4年刊の抄訳で『世界名著物語』と言うシリーズの中の一冊になります。旧仮名遣いの口語訳で数字以外の漢字には全部振り仮名が付いてます。王慶田虎が入ってるので、百二十回本ベースですな。解説も含めて235ページで百二十回本の抄訳なんで、何となく想像はできると思いますが、非常に淡々としたと言うか、味も素っ気も無い文章っす(笑)且つ、よく見ると誤字とは思えない固有名詞の間違いかも結構あるので、適当に記憶を頼りに粗筋を書いて行ったんじゃないかと思っちゃうな。武松なんてね、景陽岡で殺した虎を出門倒のあの酒屋まで引き摺ってっちゃうんだよ(笑)で、これがまた不思議なんだけど、今年2008年2月に再刊されてるんだよね、この本。しかも6,300円もするのよ(汗)何を目的にした再刊なのか、さっぱり判らないす。何故選りにも選ってこの本なんだろう??? |
| 古本小説叢刊 第二輯 水滸忠義志傳/挿増水滸全傅 中華書局 |
| 1989年に中華書局から出たシリーズの第二弾の中の二冊で、文簡事繁百十五回本の影印本になります。後ろの方は120回本みたいなタイトルだけど、やはり回数不明の簡本の残刊ですな。いずれも影印本なので、上には絵がちゃんと付いてます。簡本故に印刷も活字も良くないね、明らかに。回数が違うので、当然百二十回本と違って当たり前と言われれば当たり前だけど、微妙に違うだけって回もあったりするので、一度ゆっくり中身追いかけてみたいもんだ...ちなみに、第二輯の他の本は『両漢開国中興伝志』『包龍図判百家公案』『鍾馗全伝』『幻中真』になってます。全部だと約200種類の小説集になります。 |